(備忘録)⑤重力と量子論:最後の壁
※これは、とあるDiscord内の勉強会で議論した内容の備忘録です。話の理解がまだ曖昧だったり、結論が出ていない部分も多々あるかと思いますが、ご容赦ください。
なぜ重力だけは量子化が難しいのか?
前回の記事では、電磁気学で使われる「
試験電荷」という概念を掘り下げ、古典物理学と量子論の間に存在するギャップについて考えました。電磁気力、弱い力、強い力は、場の量子論という理論で統一的に記述されています。でも、
重力だけは、この枠組みにうまく収まらないという話を聞きました。
なぜ、重力だけが特別なのでしょうか?
これは、重力の性質が他の3つの力と根本的に違うからだと、勉強会で詳しい方が話してくれました。一般相対性理論によれば、重力は、
時空そのものが歪むことで生じる現象として記述されます。つまり、重力は、私たちがいる時空の「舞台」そのものの性質だということです。
一方、場の量子論は、時空という「舞台」の上で粒子が飛び交い、相互作用していると考えます。しかし、重力を量子化しようとすると、
時空そのものも量子的に揺らいでしまうことになり、計算がうまくいかないそうです。これを「
発散の問題」と呼ぶそうです。
💡用語の補足:発散の問題
場の量子論で重力を扱うと、計算結果が無限大になってしまう問題です。これは、重力子の相互作用がエネルギーが高くなるほど強くなり、計算が制御不能になるためと考えられています。
つまり、重力を量子化しようとすると、理論が破綻してしまうということなんですね。これは、アインシュタインの一般相対性理論と、量子力学という、現代物理学の2つの柱が、根本的に相性が悪いことを示しているのかもしれません。
重力に挑む「超弦理論」
この重力と量子論を統合する試みとして、最も有力な候補の一つが「
超弦理論(Superstring Theory)」だという話も聞きました。超弦理論は、すべての素粒子を、大きさのない「点」ではなく、
一次元の小さな「ひも(弦)」だと考えます。
この「ひも」が振動することで、様々な素粒子が生まれるという考え方です。そして、その振動パターンの一つが、なんと
重力を媒介する粒子「グラビトン(重力子)」に対応しているそうです。弦理論は、最初から重力子を内包しているため、重力を自然に量子化できる可能性があります。
超弦理論は、重力と量子論の統合を可能にするだけでなく、宇宙のすべての力を一つの理論で説明できるかもしれない、
究極の統一理論(Theory of Everything)の候補として期待されているそうです。
ただ、この理論には、私たちの宇宙とは違う
10次元(または11次元)の時空が必要になるそうです。余分な次元は「コンパクト化」されている(小さく丸まっている)と考えられているのですが、これはなかなか想像するのが難しいですね。
まとめと今後の課題
今回の勉強会で、重力という私たちの日常に不可欠な力が、量子論の世界ではいかに特殊で扱いにくい存在であるかが少しだけ分かった気がします。そして、
超弦理論のような新しい視点から、この問題を解決しようとする研究が進んでいることにも驚きました。
しかし、超弦理論にもまだ多くの謎が残されています。例えば、5つの異なる超弦理論が存在するらしいのですが、それらが実は、より大きな
M理論と呼ばれる11次元の理論の異なる側面ではないか、という話も聞きました。
これらの話を聞いて、私は「
宇宙のすべての謎を解き明かすための、最後の壁」が、この重力と量子論の統合にあるのだと強く感じました。この分野はまだ発展途上ですが、いつかこの理論が完成して、宇宙の根本原理が解き明かされる日が来ることを楽しみにしています。
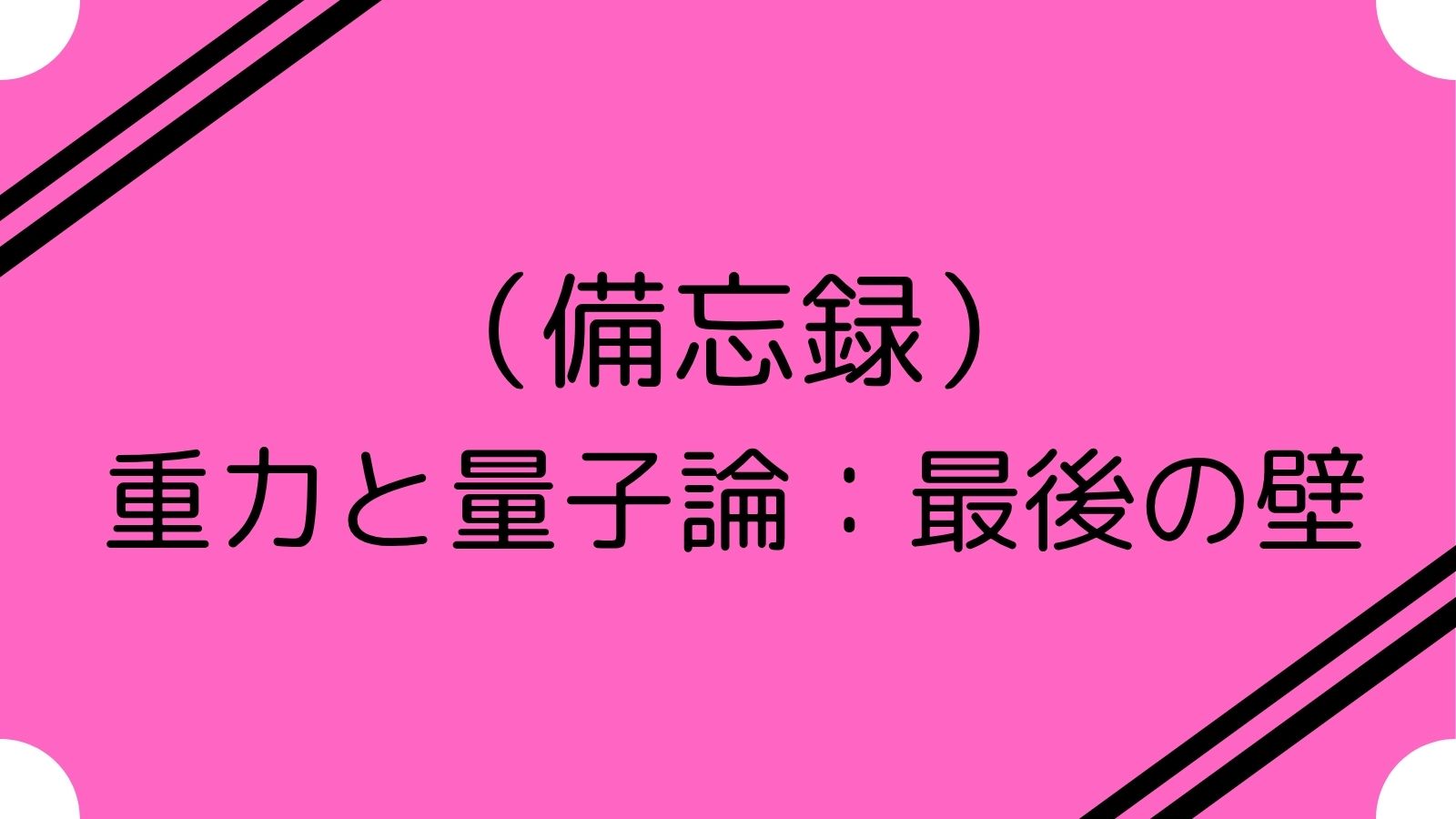 備忘録
備忘録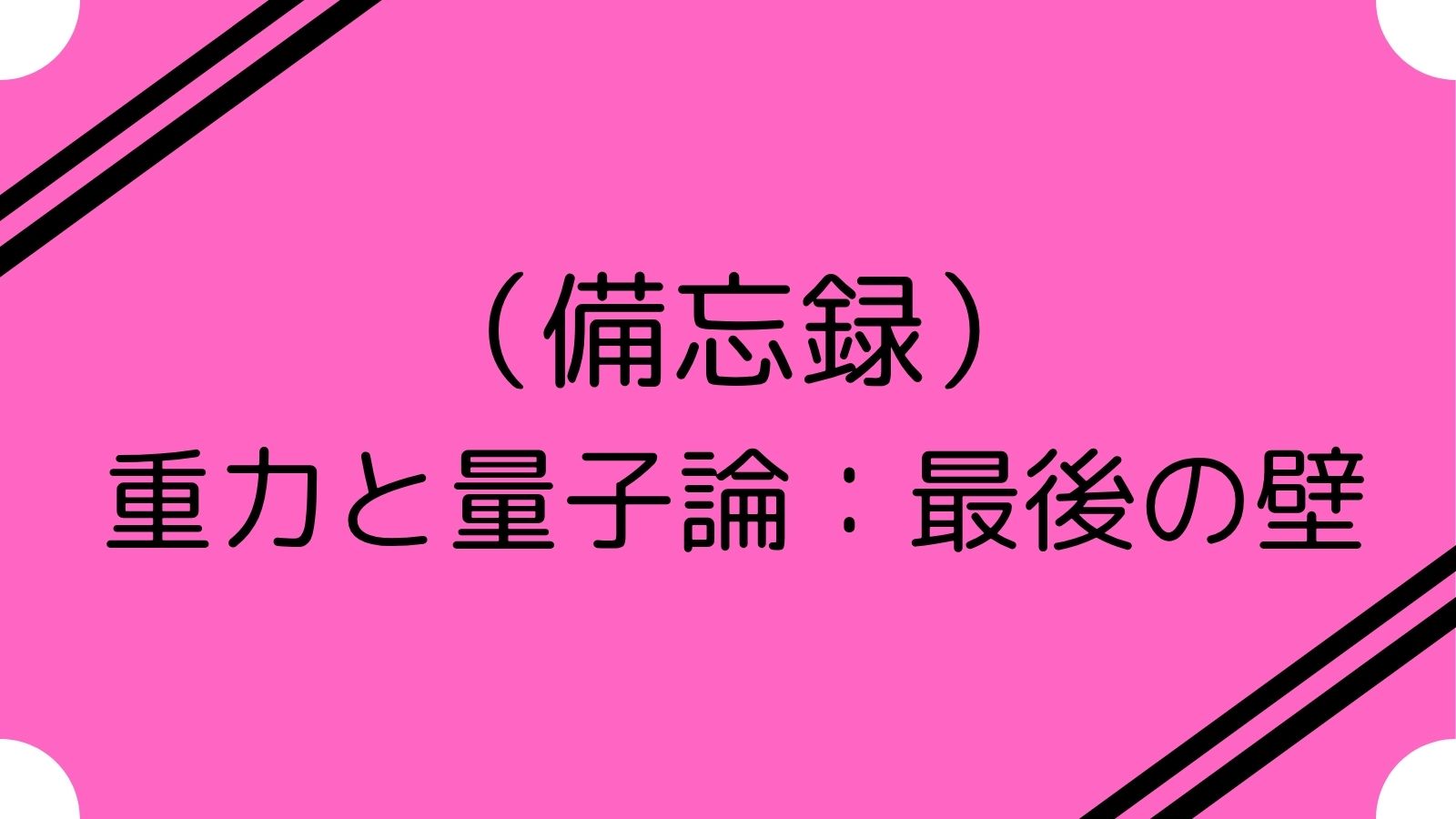 備忘録
備忘録
コメント