(備忘録)①時間とは何か?〜相対論から量子論、そして超弦理論まで〜
※これは、とあるDiscord内の勉強会で議論した内容の備忘録です。話の理解がまだ曖昧だったり、結論が出ていない部分も多々あるかと思いますが、ご容赦ください。
時間の始まりを探して
時間というものについて、改めて深く考えてみたくなりました。普段は当たり前のように過ぎていく時間ですが、物理学の世界ではその概念は一筋縄ではいきません。勉強会で進んだ勉強をされている参加者の方と対話する機会があり、その対話記録を整理してみようと思います。
まず私が気になったのは、時間と空間がセットであるという考え方についてです。
相対性理論によれば、時間と空間は「時空」という一つの連続体として結びついていると聞きました。もしそうだとしたら、宇宙の始まりであるビッグバンも、時間の始まりを意味しているのではないでしょうか?つまり、時間には始まりがあり、決してマイナス無限大の過去があるわけではないと私は考えているのですが、どうでしょうか。
勉強会で詳しい方に聞いたところでは、確かにビッグバン理論では、宇宙は約138億年前に特異点から始まったとされているため、その時点を「時間の始まり」と捉えることが多い、という情報を見ました。特異点以前の時間については、現在の物理学では説明できないため、マイナス無限大の時間は意味を持たないと解釈されることが多いようです。
時間の一方向性と対称性
次に、時間と対称性の関係について考えてみました。
物理の法則には、時間の向きを逆にしても成り立つ「時間反転対称性」があることが多いと聞いたことがあります。しかし、私たちが経験する時間の流れは明らかに一方通行です。例えば、割れたコップが自然に元に戻ることはありません。
この矛盾は、どこから来るのでしょうか?
この点について、議論の中で出てきたのですが、「対称性の破れ」という概念が深く関わっている、という情報に触れていました。特に、熱力学第二法則が鍵を握っているようです。
💡用語の補足:熱力学第二法則
孤立した系(外部とエネルギーや物質のやり取りがない系)では、エントロピー(乱雑さの度合い)は常に増大する、という法則です。
この法則によれば、宇宙のエントロピーは常に増大し続けているため、このエントロピーが増大する方向が、私たちが認識する「時間の流れ」の方向なのではないでしょうか。そう考えると、時間の一方向性という現象は、ビッグバンという秩序だった状態から宇宙が始まったことによる「対称性の破れ」として説明できるのかもしれません。
ただ、エントロピーは増大し続けると、最終的には宇宙全体が均一になり、「熱的死」と呼ばれる状態に到達する可能性があるとも聞きます。この状態は、ビッグバンとは逆に、究極に対称な状態と考えることもできるのではないでしょうか?
そうだとすると、宇宙は対称性が破れた状態から始まり、時間の流れと共にエントロピーを増大させ、最終的には再び対称性が保たれた状態に戻っていく、という循環のような見方もできるのかもしれません。私はそう思っているのですが、この考えは正しいでしょうか。
エントロピーと情報の不可思議な関係
エントロピーというと、熱や統計物理学のイメージが強いのですが、時間の流れと結びついていると聞いて興味が湧きました。そして、さらに情報とも関係があるという話を聞いて驚いています。
情報とエントロピーがなぜ関係するのか、そのヒントは「マクスウェルのデーモン」という思考実験にあると聞きました。この実験では、デーモンが分子を選別することで、エントロピーを減少させられるように見えます。しかし、その後の研究で、デーモンが分子を観測し、その情報を消去する行為自体にエントロピーの増大を伴うことが示されたそうです。
この話は、情報の物理的な側面を示していると思います。そして、この「情報の消去」によるエントロピー増大は、「ランダウアーの原理」として定式化されているという情報を見ました。
💡数式:ランダウアーの原理
1ビットの情報を消去するたびに、最低でも/[k_{B} T /log 2/]という熱を外界に放出する必要がある、という原理です。情報の操作には熱力学的なコストがかかることを示します。
この原理から考えると、コンピュータのメモリでさえ、情報の保存や消去には熱が発生しているということになるのでしょうか?
このエントロピーと情報の関係は、さらに量子力学の観測問題とも繋がっているそうです。
量子力学では、粒子は複数の状態が同時に存在する「重ね合わせの状態」にあるのですが、観測すると一つの状態に定まります。この「観測」という行為が、実は粒子の持つ情報が、観測装置や周囲の環境に拡散していくこと(デコヒーレンス)を意味しているという情報を見ました。
この情報の拡散が、エントロピーの増大そのものだと考えると、観測問題における「状態の収縮」という現象が、少しだけ腑に落ちる気がします。ただ、この辺りの話は非常に難解で、私の理解が正しいのかはまだ確信が持てません。
観測という行為の再考
量子力学における「観測」の概念については、特に疑問に思っていることがあります。
私たちは、目で見ることを「観測」と呼びますが、量子力学で言う「観測」は少し違うのではないでしょうか。単に「見る」という受動的な行為ではなく、観測しようとして対象に光を当てるなどの「相互作用」を意図的に加える行為が、量子力学的な観測なのではないか、と感じています。
普段、マクロな物質を観測する際には、この相互作用による影響は無視できるほど小さいです。しかし、電子のようなミクロな粒子では、観測のための相互作用が、粒子の元の状態を大きく変えてしまいます。
電磁気学で、電場を測定するために「試験電荷」という概念を使いますが、これにも同様の疑問を感じています。
これらは、物理学の理想化されたモデルと現実の観測との間のギャップを示しているように思えます。
しかし、勉強会の先輩方の話では、これらの疑問は、古典的な電磁気学の限界であり、場の量子論や量子電磁気学といった、より高度な分野で議論されるテーマだという情報を見ました。
どうやら、この分野に進むには、もっと多くのことを学ぶ必要があるようです。しかし、今回の勉強会を通じて、時間、エントロピー、情報、観測といった一見バラバラに見える概念が、一つの大きな枠組みの中で深く結びついていることが少しだけ見えてきた気がします。
この続きは、また次の機会にまとめてみようと思います。
参考文献
記事を書くときに、参照したので載せておきます。

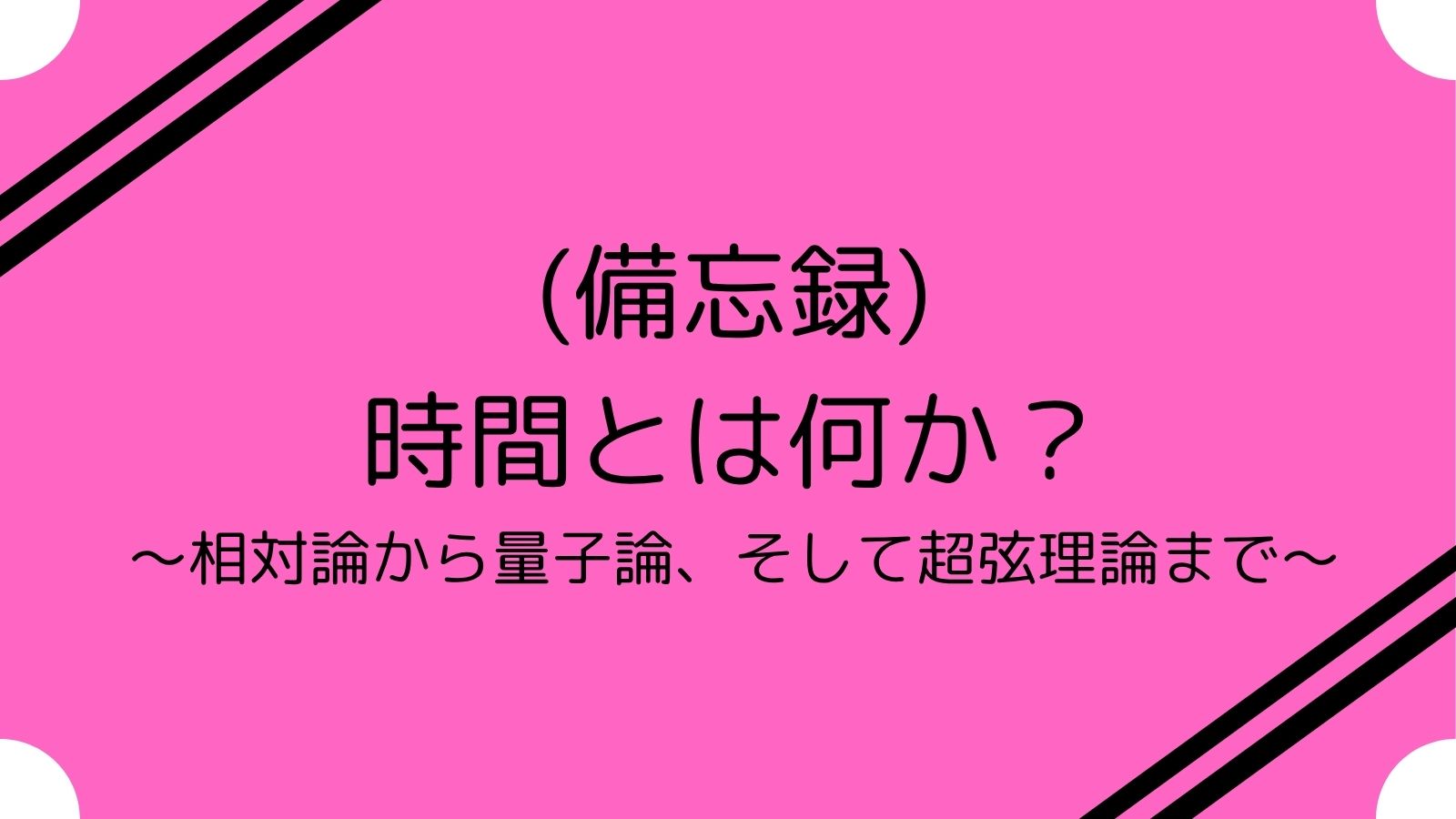


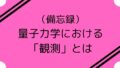
コメント