(備忘録)⑩超弦理論における高次元とコンパクト化
※これは、とあるDiscord内の勉強会で議論した内容の備忘録です。話の理解がまだ曖昧だったり、結論が出ていない部分も多々あるかと思いますが、ご容赦ください。
なぜ高次元は私たちの目に触れないのか?
前回は、
超弦理論がなぜ必要かという話を書きました。素粒子を点ではなく「ひも(弦)」と考えることで、量子論と重力の矛盾を解消し、
統一理論への道を開く可能性があるというものでした。しかし、この超弦理論が予言する宇宙は、私たちが見ている4次元(3次元空間+時間)だけではないんですよね。
なんと、超弦理論は
10次元(または11次元)の時空を予言します。では、残りの6つ(または7つ)の次元はどこにあるのでしょうか?
この見えない次元は、私たちの周りに「コンパクト化」されて、非常に小さく丸まっていると考えられています。
この「コンパクト化」という概念が、なかなか直感的に理解しにくいのですが、勉強会で聞いた例え話がとても分かりやすかったので、ここにまとめてみます。
例え話で考える「コンパクト化」
この概念を理解するためには、私たちのスケールと、ミクロなスケールで世界がどう見えるか、という視点の違いが重要になってきます。
まるで、カーペットや芝生の上を歩くアリのようなものです。
私たち人間が遠くからカーペットや芝生を見ると、それは平らな2次元の面に見えます。しかし、その上にいるアリにとっては、繊維や草の一本一本がそびえ立つ、複雑な3次元の空間が広がっています。アリは、私たちには見えない、もう一つの次元(高さ)を自由に動き回っているのです。
これと同じように、私たちの宇宙には、私たちが認識できる3つの空間次元に加えて、
非常に小さく丸まっている(コンパクト化された)高次元が存在している、と超弦理論は考えます。
また、もう一つの例えとして、紙を筒状に丸めていく話も分かりやすかったです。
紙を筒状に丸めて、半径をどんどん小さくしていくと、遠くから見るとそれは一本の線のようにしか見えなくなる。
でも、その「線」の上を歩くアリにとっては、筒の表面をぐるぐると回ることで、もう一つの次元がそこに存在していることが分かります。私たちの宇宙も、この丸まった筒のように、高次元が小さく丸まって存在しているのかもしれません。
統一理論「M理論」への道
この
「コンパクト化」という概念は、
M理論を考える上でも非常に重要になってきます。超弦理論には、5つの異なるモデルが存在しますが、それらが実は、より一般的な11次元の
M理論の異なる側面である、という話を書きました。
この11次元のM理論が、どのような形で10次元の超弦理論へとコンパクト化されるのか、その多様な可能性が、5つの異なる超弦理論を生み出しているのかもしれません。 M理論の探求は、まだ始まったばかりですが、このコンパクト化の概念が、
重力と量子論を統合する究極の統一理論の鍵を握っているように感じます。
まとめと今後の課題
今回の勉強会で、
超弦理論が予言する高次元空間が、なぜ私たちの目に触れないのか、という疑問が少しだけ解決しました。それは、高次元が
コンパクト化されて、非常に小さく丸まっているからだ、という考え方です。
しかし、この高次元の形状は、具体的にどうなっているのでしょうか?そして、その形状が、私たちが知る物理法則や、素粒子の性質を決定している、という話も聞いたのですが、これはどういうことなのでしょうか?
次回は、この
「高次元の形状と物理法則の関係」について、さらに議論を深めていきたいと考えています。
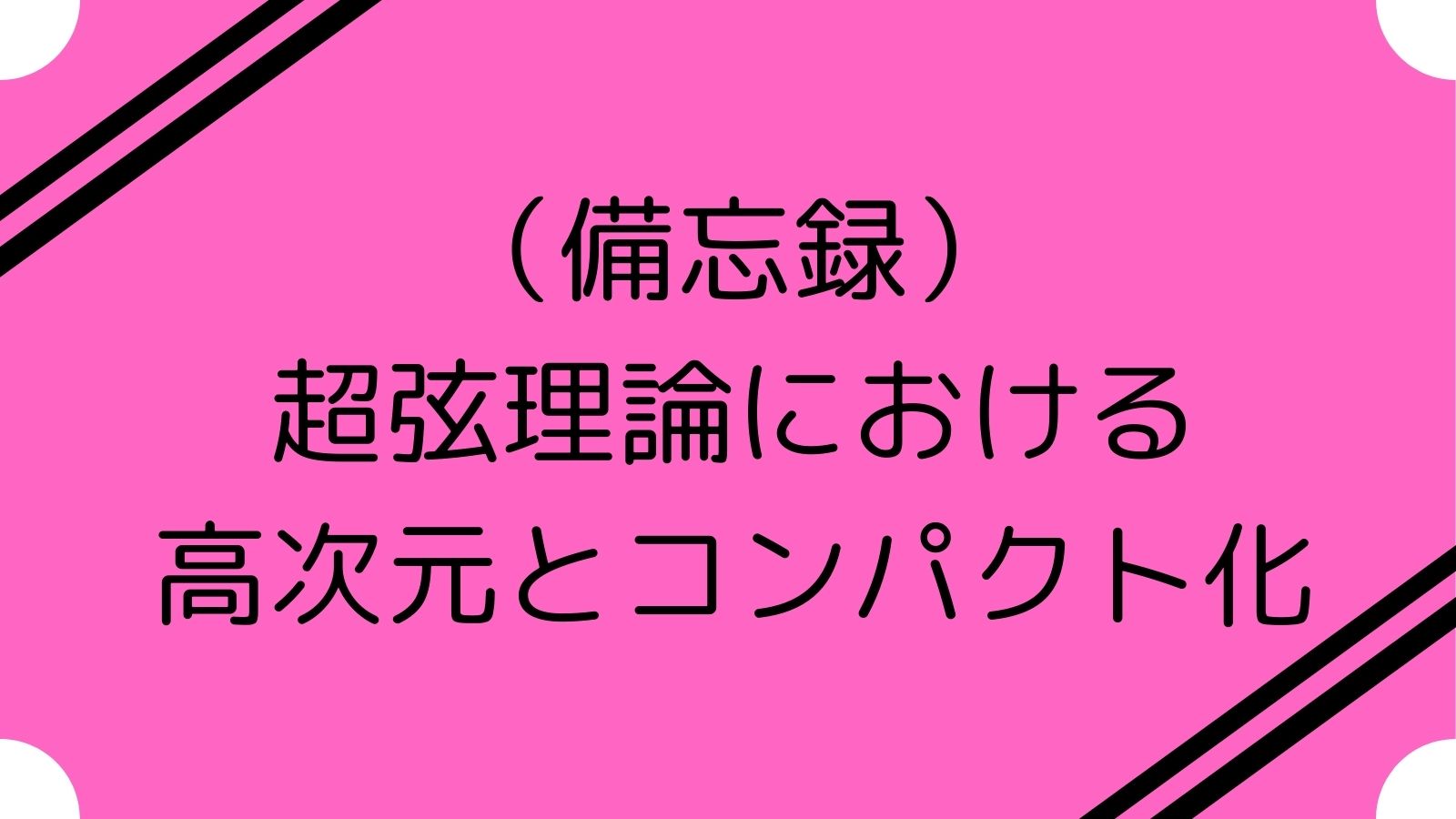 備忘録
備忘録


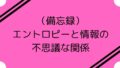
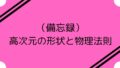
コメント