(備忘録)④電磁気学と量子論のギャップ
※これは、とあるDiscord内の勉強会で議論した内容の備忘録です。話の理解がまだ曖昧だったり、結論が出ていない部分も多々あるかと思いますが、ご容赦ください。
電磁気学における「試験電荷」という理想化
前回の記事で、量子力学における「観測」の概念が、私たちの日常的な感覚と大きく異なることを書きました。量子力学では、観測しようとすると、観測対象に必ず
相互作用が起こり、その状態を変化させてしまいます。この考え方は、古典物理学の理想化されたモデルに疑問を投げかけているように思います。
その典型的な例が、電磁気学で使われる「
試験電荷」という概念です。これは、電場を測定するために用いられる、
大きさが無限に小さく、元の電場に影響を与えないとされる理想的な電荷のことです。高校や大学の物理で、電場の強さ$\vec{E}$を求める際に、この試験電荷$q$が受ける力$\vec{F}$を使って、$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$と習いました。でも、この考え方には、いくつかの疑問が浮かびます。
1. 本当に試験電荷は元の電場に影響を与えないのか?
どんなに小さな電荷でも、そこには電場が発生するはずです。その電場が、元の電場をわずかでも変化させてしまうのではないでしょうか?2. 試験電荷の動きをどうやって「観測」するのか?
試験電荷が受ける力を測定するには、何らかの観測装置が必要です。その観測装置が、量子力学的な意味での相互作用を起こし、試験電荷の元の状態を大きく変えてしまうのではないか?
これらの疑問は、古典的な電磁気学の枠組みでは答えるのが難しいように感じます。
古典物理学と量子物理学の境界
これらの疑問は、
古典物理学と量子物理学の間に存在するギャップを示しているように思えます。古典物理学は、物質や場の性質を連続的なものとして扱いますが、量子物理学は、それらが離散的なエネルギーの「量子」として存在すると考えます。
電磁気学の
電磁場も、実は
光子(フォトン)という量子的な粒子の集まりとして捉えることができます。これが
場の量子論の考え方です。
💡用語の補足:場の量子論
場(電磁場など)を量子力学のルールに従って記述する理論です。場を量子化することで、光子のような粒子が自然に導き出されます。
場の量子論の視点から見ると、試験電荷の周りにある電場は、
仮想的な光子が飛び交うことで生じていると考えられます。そして、試験電荷を置くという行為は、この光子のやり取りを変化させることになります。つまり、
「試験電荷は元の電場に影響を与えない」という理想化は、量子論の世界では成り立たないという結論に至るようです。
これは、古典的な電磁気学の考え方が、ミクロな世界では通用しないことを示しているのだと思います。私たちは日常的に電磁気の法則を体験していますが、その背後には、もっと複雑で不思議な量子力学の世界が広がっているんですね。
まとめと今後の課題
今回の勉強会で、古典物理学の便利なモデルである「試験電荷」が、量子論の視点から見ると多くの課題を抱えていることが分かりました。そして、古典物理学と量子物理学の間には、
「場の量子論」というより高度な理論が必要なギャップが存在していることを再認識しました。
しかし、物理学にはもう一つ重要な理論があります。それが「
重力」を扱う
一般相対性理論です。
場の量子論は、電磁気力、弱い力、強い力をうまく説明していますが、重力だけはうまく統合できていません。
なぜ重力だけが量子化できないのでしょうか?
次回は、この「
量子重力理論」の探求について、さらに議論を深めていきたいと考えています。

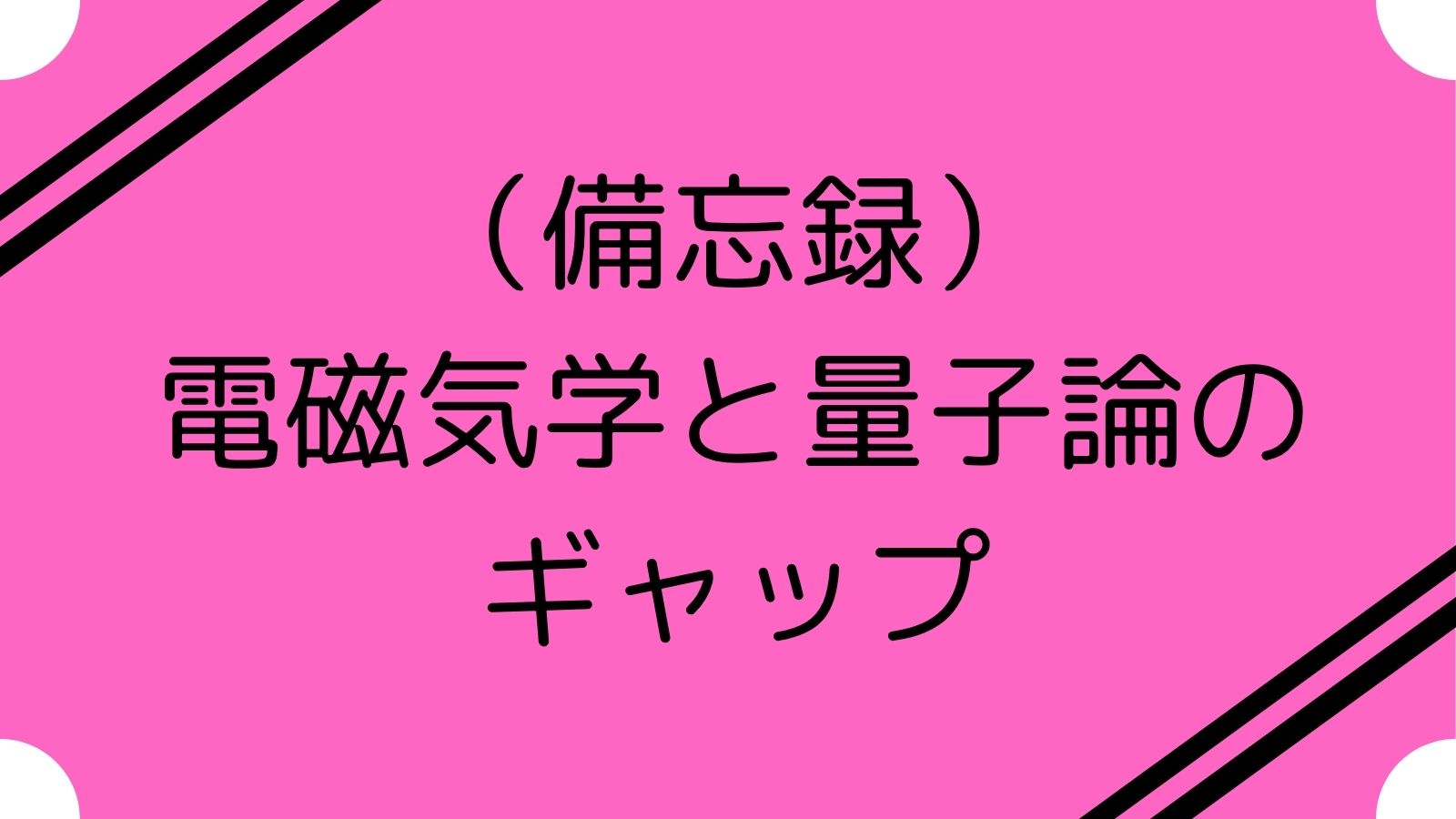


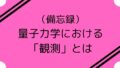
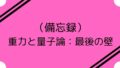
コメント