(備忘録)③量子力学における「観測」とは
※これは、とあるDiscord内の勉強会で議論した内容の備忘録です。話の理解がまだ曖昧だったり、結論が出ていない部分も多々あるかと思いますが、ご容赦ください。
観測という行為の再考
前回の勉強会でも少し触れたのですが、量子力学における「観測」の概念について、どうしても深く考えてしまいます。私たちは、目で見ることを「観測」と呼びますが、量子力学で言う「観測」は少し違うのではないでしょうか。単に「見る」という受動的な行為ではなく、
観測しようとして対象に光を当てるなどの「相互作用」を意図的に加える行為が、量子力学的な観測なのではないかと、私は感じています。
普段、マクロな物質を観測する際には、この相互作用による影響は無視できるほど小さいです。しかし、電子のようなミクロな粒子では、観測のための相互作用が、粒子の元の状態を大きく変えてしまいます。
この考え方、実は「
ハイゼンベルクの不確定性原理」に通じる部分があるように思えます。
💡数式:ハイゼンベルクの不確定性原理
粒子の位置を$x$、運動量を$p$とすると、その不確かさ$\Delta x$と$\Delta p$の間には、以下の関係が成り立ちます。
$\Delta{x}\Delta{p}\ge\frac{\hbar}{2}$
ここで、$\hbar$はディラック定数と呼ばれるものです。
この式が意味しているのは、
粒子の位置と運動量を同時に、かつ正確に測定することは不可能だということです。位置を正確に測ろうとすると、運動量が不確かになり、運動量を正確に測ろうとすると、位置が不確かになります。これは、観測という相互作用が、粒子の状態を必ず「乱してしまう」ことを示しているのではないでしょうか。
観測問題とエントロピー
前回の記事で、
エントロピーと情報が関係しているという話を書きました。この考え方から、量子力学の「観測問題」を紐解くヒントが見えてきたように思います。
量子力学では、粒子は複数の状態が同時に存在する「重ね合わせの状態」にあるのですが、観測すると一つの状態に定まります。この現象は「
波動関数の収縮」と呼ばれ、多くの物理学者を悩ませてきた問題です。
議論の中で、この「観測」という行為が、実は粒子の持つ情報が、観測装置や周囲の環境に拡散していくこと(
デコヒーレンス)を意味している、という話が出ました。
💡用語の補足:デコヒーレンス
量子状態が、環境との相互作用によって、重ね合わせの状態を失い、古典的な状態へと変化していく現象です。
この
情報の拡散が、エントロピーの増大そのものだと考えると、観測問題における「状態の収縮」という現象が、少しだけ腑に落ちる気がします。つまり、観測とは、系が持っていた量子的な情報が、外部の環境と相互作用することで「乱雑さ」として拡散していくプロセスであり、その結果、一つの古典的な状態として現れる、という見方です。
ただ、この考え方でも「なぜ、特定の状態に収縮するのか?」という根本的な疑問には、まだ答えが出ていないようです。あくまで、観測が引き起こす現象をエントロピーの視点から説明する、一つのアプローチに過ぎないのかもしれません。
まとめと今後の課題
今回の勉強会で、量子力学の観測という行為は、単なる「見る」ことではなく、
ミクロなレベルでの相互作用であり、その相互作用が粒子の不確かさを生み出すことが分かりました。そして、観測問題における「波動関数の収縮」も、エントロピーの増大と関連している可能性が示唆されました。
しかし、この話にはまだ続きがあるんですよね。古典的な電磁気学で使われる「
試験電荷」のような、相互作用を無視して観測するという理想化されたモデルは、量子力学の視点から見ると、い
ったいどうなるのでしょうか?
次回は、この「試験電荷」の概念を掘り下げて、古典物理学と量子物理学の境界について、さらに議論を深めていきたいと考えています。

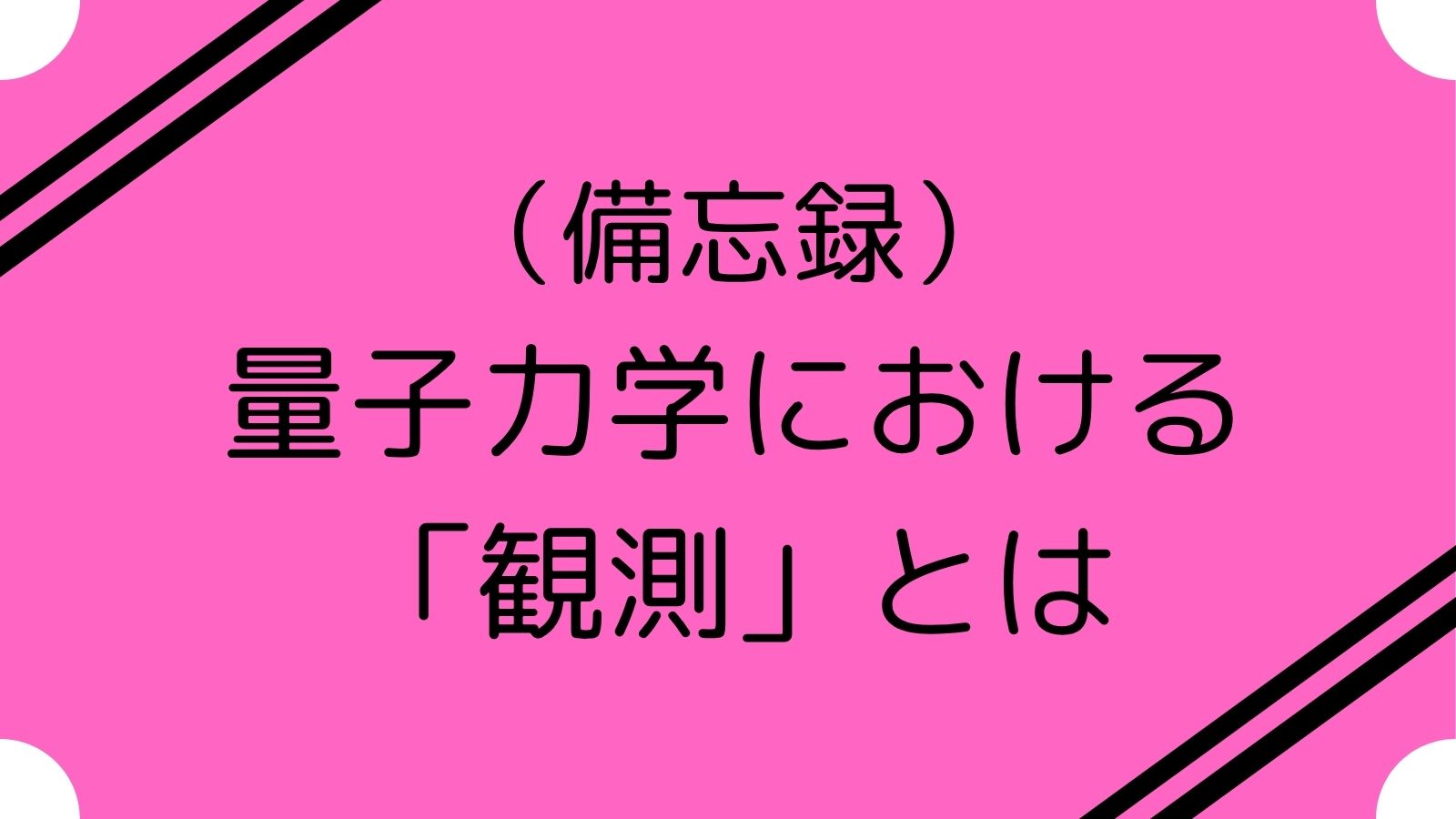


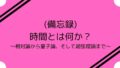
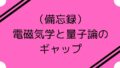
コメント