前回は「時間の遅れ」と「固有時間」について解説しました。
今回は、特殊相対性理論の最も有名な思考実験の一つである「双子のパラドックス」と、それに関連する「ローレンツ収縮」について掘り下げていきたいと思います。
双子のパラドックス
「双子のパラドックス」は、特殊相対性理論の時間の遅れの考え方を、直感に反する形で示す思考実験です。この実験は、宇宙を旅する双子(次郎)と地球に残る双子(太郎)の間の時間の進み方の違いを扱います。
- 実験の設定:太郎は地球に留まり続け、次郎は高速ロケットに乗って宇宙の旅に出て、最終的に地球に戻ってきます。
- 時間の遅れによる矛盾:特殊相対性理論によれば、互いに動いている相手の方が時間の進みが遅く見えるはずです。しかし、この実験では、どちらがより若くなるかという矛盾が生じます。
このパラドックスの鍵は、「対称性の破れ」にあります。太郎は常に慣性系(等速直線運動)に留まっているのに対し、次郎は途中で向きを変えて地球に戻るために加速運動をしています。前回解説した「固有時間」の性質を思い出してください。自由粒子(慣性系にいる粒子)が通る世界線が最も長い固有時間を経過するという性質があります。つまり、加速運動をした次郎の方が経過した時間が少なくなり、地球に戻ってきたとき、太郎よりも若くなるのです。
ローレンツ収縮
特殊相対性理論のもう一つの有名な現象が「ローレンツ収縮」です。これは、高速で動く物体の長さが、静止している観測者から見て、運動方向に対して縮んで見えるという現象です。
この現象は、ローレンツ変換の式を用いることで数学的に証明できます。例えば、電車の中に置かれた棒の長さを、動いている電車内と地上からそれぞれ測定すると、地上から測った棒の長さが本来の長さよりも短くなることが示されます。
ローレンツ収縮の導出
静止している観測者Sと、$x$軸方向に速度$v$で移動している観測者S’を考えます。S’の系では、ある棒が$L_0$の長さを持つとします。この棒の両端の座標は$x’_1$と$x’_2$で、その長さは$L_0 = x’_2 – x’_1$です。この棒の長さを、静止している観測者Sが測定することを考えます。
Sの系から見ると、棒は動いているため、その長さを正確に測るためには、棒の両端を同時に($t_1 = t_2 = t$の瞬間に)測定する必要があります。
ここで、ローレンツ変換の式を思い出しましょう。
この2つの式から、$x’_2 – x’_1$を計算します。
整理すると、
となります。ここで、同時に測定するという条件$t_1 = t_2 = t$を代入すると、$t_2 – t_1 = 0$となり、式は以下のようになります。
ここで、$x’_2 – x’_1 = L_0$(棒の静止時の長さ)、$x_2 – x_1 = L$(S系から見た棒の長さ)とすると、
この式を$L$について解くと、
となり、$\gamma = 1 / \sqrt{1 – v^2/c^2}$は常に1以上なので、$L < L_0$となります。この式は、運動している物体の長さは、静止している観測者から見て縮んで見えることを示しています。これが「ローレンツ収縮」です。
次回のノートでは、特殊相対性理論の概念をさらに深めるために、「4元速度」と「4元運動量」について解説していきます。
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。
-
- 一般相対論入門 改訂版 : [須藤 靖 (著)]
- 第3版 シュッツ 相対論入門 I 特殊相対論 : [江里口 良治 (翻訳), 二間瀬 敏史 (翻訳), Bernard Schutz (著) ]
- 第3版 シュッツ 相対論入門 II 一般相対論: [江里口 良治 (翻訳), 二間瀬 敏史 (翻訳), Bernard Schutz (著)]
- 相対性理論入門講義 (現代物理学入門講義シリーズ 1) [風間 洋一 (著)]
- 基幹講座 物理学 相対論 [田中 貴浩 (著)]
- 時空の幾何学:特殊および一般相対論の数学的基礎[James J. Callahan (著), 樋口 三郎 (翻訳)]
- これならわかる工学部で学ぶ数学 新装版: [千葉 逸人]
- 基幹講座 物理学 相対論: [田中 貴浩]
これまでの相対論ノート一覧
- 相対論ノート#1:空間の曲がりを数学的に表すには
- 相対論ノート#2:特殊相対性理論の二つの原理
- 相対論ノート#3:ローレンツ変換とその導出
- 相対論ノート#4:ミンコフスキー時空
- 相対論ノート#5:固有時間と時間の遅れ
- 相対論ノート#6:双子のパラドックスとローレンツ収縮
- 相対論ノート#7:4元速度と4元運動量
- 相対論ノート#8:保存カレントと保存チャージ
- 相対論ノート#9:エネルギーと運動量テンソル
- 相対論ノート#10:等価原理と一般相対性原理
- 相対論ノート#11:リーマン幾何学の基礎
- 相対論ノート#12:スカラー、ベクトル、テンソルの変換則
- 相対論ノート#13:テンソルの縮約と普遍性
- 相対論ノート#14:計量テンソル
- 相対論ノート#15:測地線とクリストッフェル記号
- 相対論ノート#16:共変微分とリーマン距離率テンソル
- 相対論ノート#17:リッチテンソル、アインシュタインテンソル、そしてアインシュタイン方程式
- 相対論ノート#18:アフィン接続係数と座標変換則
- 相対論ノート#19:等価原理とアフィン接続係数
- 相対論ノート#20:ベクトルの平行移動とテンソルの平行移動
- 相対論ノート#21:共変微分
- 相対論ノート#22:共変微分の性質
- 相対論ノート#23:共変微分の発散
- 相対論ノート#24:リーマン曲率テンソルの定義
- 相対論ノート#25:リーマン曲率テンソルの幾何学的意味
- 相対論ノート#26:リーマン曲率テンソルの対称性
- 相対論ノート#27:リッチテンソルとアインシュタインテンソルの導出
- 相対論ノート#28:アインシュタイン方程式の厳密解:シュワルツシルト解
- 相対論ノート#29:重力レンズ効果
- 【補足】ビアンキ恒等式とアインシュタインテンソル – 第30回
- 【補足】弱い重力場中の粒子の運動 – 第31回
- 【補足】重力による時間の遅れと重力赤方偏移 – 第32回
- 【補足】水星の近日点移動の現象 – 第33回
- 【補足】タキオン – 第34回
- 【補足】重力波 – 第35回

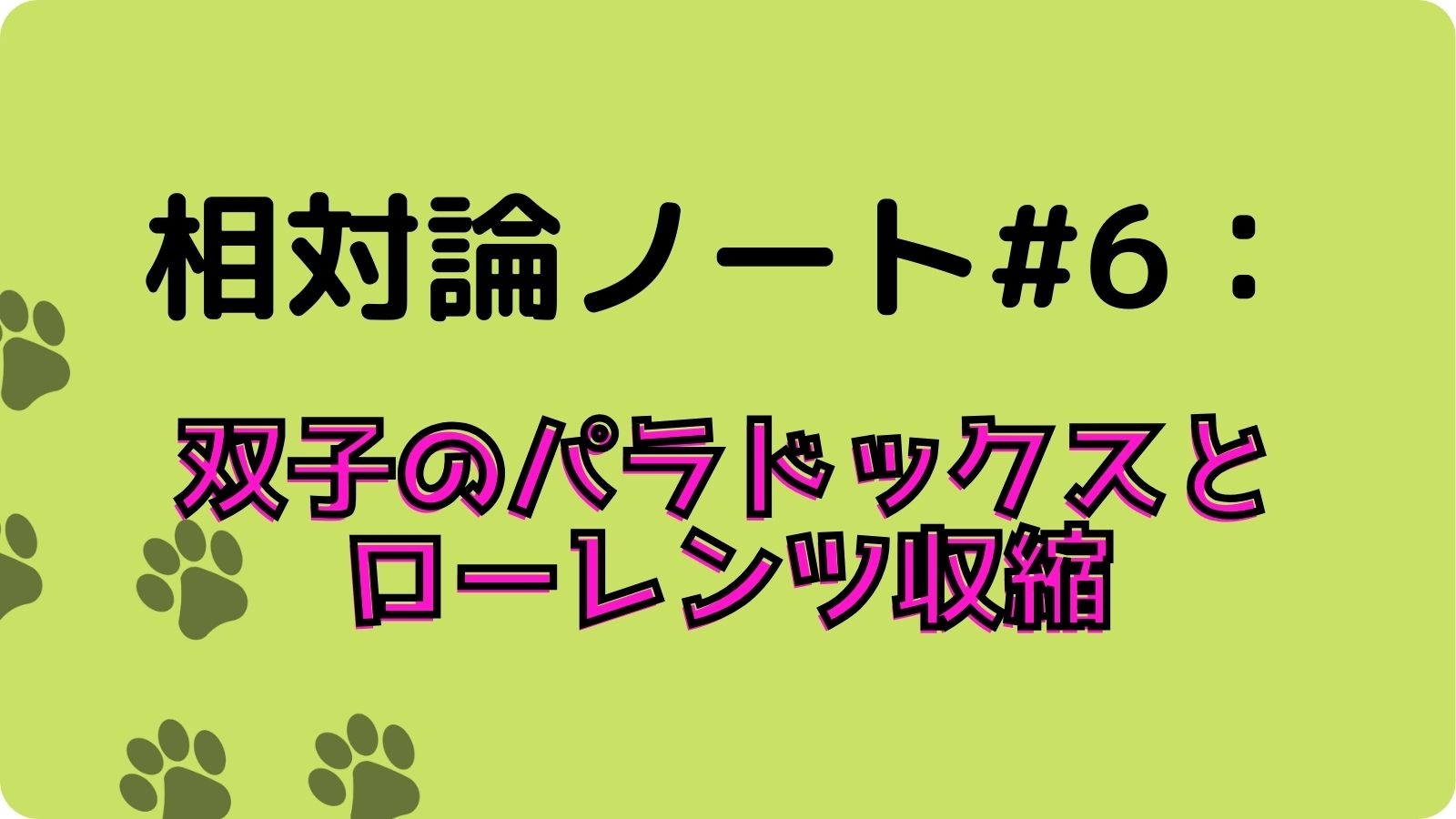


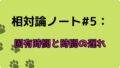
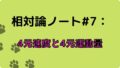
コメント