このブログ記事は、私が個人的に勉強した相対性理論の入門的な内容をまとめたものです。今回は、一般相対性理論の第一歩として、「空間の曲がり」を数学的にどのように表現するかについてです。
一般相対性理論は、「重力に関する理論」です。ニュートン力学では、重力は物体と物体が引き合う力として考えますが、一般相対性理論では、少し違った見方をします。重力現象は、「時空の歪み」として扱うのです。
例えば、太陽のような大きな質量を持つ天体があると、その周囲の時空は歪み、その歪みに沿って惑星が運動している、と考えるわけです。
この考え方では、時空の歪みをどうやって数学的に記述するかが非常に重要になります。このブログの最終的な目標は、アインシュタイン方程式を自分で解けるようになることです。そのためには、まず時空の曲がりを表現するための基本的な数学ツールを学ぶ必要があります。
※本記事では、分かりやすさのため「空間の曲がり」という言葉を使いますが、実際には「時空の曲がり」を扱っていることを心に留めておいてください。
空間の距離を測る「線素(Line Element)」
まず、「線素(Line Element)」という概念を導入します。これは、微小な2点間の距離を定義するものです。例えば、私たちが普段扱う平らな空間(ユークリッド空間)では、2次元の平面上の点$P(x, y)$とそこから少し離れた点$Q(x+dx, y+dy)$の距離$ds$は、ピタゴラスの定理を使って求めることができます。
$$ds^2 = dx^2 + dy^2$$
これを3次元に拡張しても同様です。
$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$
ところが、地球のような「曲がった空間(球面)」では、ピタゴラスの定理はそのまま使えません。地球上のある点から少しだけ東に、そして少しだけ北に移動したとしても、その距離の2乗が単純な足し算にはならないのです。
このように、曲がった空間でも距離を正しく測るために、この$ds^2$の式を拡張して使います。この拡張された$ds^2$の式を見ることで、その空間がどのように曲がっているかの情報を得ることができるわけです。
そして、この式に含まれる「計量(Metric)」という係数$g_{ij}$が、空間の曲がりを表現する上で非常に重要な役割を果たします。計量については後ほど詳しく解説します。
平坦な空間の線素の計算例
ここから、平坦な3次元空間の線素$ds^2$を、直交座標系と極座標系で表現する計算例を見ていきましょう。
1.直交座標系での線素
これは先ほども述べたように、単純なピタゴラスの定理の拡張です。位置ベクトル$\vec{r}$が$(x, y, z)$で表されるとき、微小変位$d\vec{r}$は$(dx, dy, dz)$です。よって、$ds^2 = |d\vec{r}|^2$は次のようになります。
$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$
2.極座標系での線素
直交座標系を、極座標系$(r, \theta, \phi)$に変換してみましょう。各座標の関係は以下のようになります。
$$\begin{cases} x = r \sin\theta \cos\phi \\ y = r \sin\theta \sin\phi \\ z = r \cos\theta \end{cases}$$
この式を$dx, dy, dz$に変換するために、各座標を$r, \theta, \phi$で偏微分します。ここで合成関数の微分(チェインルール)を使います。
$$\begin{aligned} dx &= \frac{\partial x}{\partial r}dr + \frac{\partial x}{\partial \theta}d\theta + \frac{\partial x}{\partial \phi}d\phi \\ &= (\sin\theta\cos\phi)dr + (r\cos\theta\cos\phi)d\theta + (-r\sin\theta\sin\phi)d\phi \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} dy &= \frac{\partial y}{\partial r}dr + \frac{\partial y}{\partial \theta}d\theta + \frac{\partial y}{\partial \phi}d\phi \\ &= (\sin\theta\sin\phi)dr + (r\cos\theta\sin\phi)d\theta + (r\sin\theta\cos\phi)d\phi \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial r}dr + \frac{\partial z}{\partial \theta}d\theta + \frac{\partial z}{\partial \phi}d\phi \\ &= (\cos\theta)dr + (-r\sin\theta)d\theta + (0)d\phi \end{aligned}$$
次に、これらの$dx, dy, dz$を$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$に代入します。ここで、アインシュタインの縮約規則を導入すると、計算が非常に簡潔になります。
アインシュタインの縮約規則
この規則は、式の中に同じ添え字が上と下にペアで現れた場合、その添え字について自動的に和を取るというものです。例えば、$x_i y^i$という式があった場合、これは$\sum_i x_i y^i$を意味します。つまり、$x_1y^1 + x_2y^2 + \dots$ということです。この和を取る操作を「縮約」、和に使われる添え字を「ダミー添え字」と呼びます。
ダミー添え字は、式を変形する際に別の文字に自由に変更することができます。(例えば、$x_i y^i$の添え字を$i→q$のように変更して$x_q y^q$としまっても、同じ添え字で縮約を取ることを課せば、同じ式であることが分ると思います。)
この規則を使うと、$ds^2$の式は$g_{ij}dx^idx^j$と書くことができます。ここで$g_{ij}$は計量テンソル、$dx^i$は座標の微小変化を表します。この縮約規則は、一般相対性理論の計算を非常にシンプルにしてくれるため、今後も頻繁に登場します。
さて、話を元に戻して、極座標系での線素を計算していきましょう。少し複雑ですが、頑張って計算してみます。
$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$
ここで、$dx^2$を計算します。
$$\begin{aligned} dx^2 &= (\sin\theta\cos\phi)^2dr^2 + (r\cos\theta\cos\phi)^2d\theta^2 + (-r\sin\theta\sin\phi)^2d\phi^2 \\ &+ 2(\sin\theta\cos\phi)(r\cos\theta\cos\phi)drd\theta \\ &+ 2(\sin\theta\cos\phi)(-r\sin\theta\sin\phi)drd\phi \\ &+ 2(r\cos\theta\cos\phi)(-r\sin\theta\sin\phi)d\theta d\phi \end{aligned}$$
$dy^2$と$dz^2$も同様に計算し、全て足し合わせます。すると、$drd\theta, drd\phi, d\theta d\phi$のようなクロス項がうまく打ち消しあってゼロになることがわかります。
例えば、$drd\theta$の係数を見てみましょう。$dx^2$からは$2r\sin\theta\cos\theta\cos^2\phi$、$dy^2$からは$2r\sin\theta\cos\theta\sin^2\phi$、$dz^2$からは$-2r\sin\theta\cos\theta$となります。これらを足し合わせると、
$$2r\sin\theta\cos\theta(\cos^2\phi + \sin^2\phi – 1) = 2r\sin\theta\cos\theta(1-1) = 0$$
となります。他のクロス項も同様にゼロになります。最終的に、$dr^2, d\theta^2, d\phi^2$の項だけが残ります。
$ds^2$の係数をまとめると、
・$dr^2$の係数:$\sin^2\theta\cos^2\phi + \sin^2\theta\sin^2\phi + \cos^2\theta = \sin^2\theta(\cos^2\phi+\sin^2\phi) + \cos^2\theta = \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
・$d\theta^2$の係数:$r^2\cos^2\theta\cos^2\phi + r^2\cos^2\theta\sin^2\phi + r^2\sin^2\theta = r^2\cos^2\theta(\cos^2\phi+\sin^2\phi) + r^2\sin^2\theta = r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta=r^2$
・$d\phi^2$の係数:$r^2\sin^2\theta\sin^2\phi + r^2\sin^2\theta\cos^2\phi = r^2\sin^2\theta(\sin^2\phi+\cos^2\phi)=r^2\sin^2\theta$
となり、最終的な式は以下のようになります。
$$ds^2 = dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\phi^2$$
このように、同じ平坦な空間であっても、座標系を変えるだけで線素の形が変わることが分かります。この式の$dr^2, d\theta^2, d\phi^2$の前の係数が、計量テンソルの成分に相当するわけです。この計量が、空間の幾何学的な情報をすべて含んでいるのです。
次回のノートでは、特殊相対性理論の基本的な原理である「相対性原理」と「光速度不変の原理」について、ニュートン力学と比較しながら詳しく見ていきたいと思います。
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。
- 一般相対論入門 改訂版 : [須藤 靖 (著)]
- 第3版 シュッツ 相対論入門 I 特殊相対論 : [江里口 良治 (翻訳), 二間瀬 敏史 (翻訳), Bernard Schutz (著) ]
- 第3版 シュッツ 相対論入門 II 一般相対論: [江里口 良治 (翻訳), 二間瀬 敏史 (翻訳), Bernard Schutz (著)]
- 相対性理論入門講義 (現代物理学入門講義シリーズ 1) [風間 洋一 (著)]
- 基幹講座 物理学 相対論 [田中 貴浩 (著)]
- 時空の幾何学:特殊および一般相対論の数学的基礎[James J. Callahan (著), 樋口 三郎 (翻訳)]
- これならわかる工学部で学ぶ数学 新装版: [千葉 逸人]
これまでの相対論ノート一覧
- 相対論ノート#1:空間の曲がりを数学的に表すには
- 相対論ノート#2:特殊相対性理論の二つの原理
- 相対論ノート#3:ローレンツ変換とその導出
- 相対論ノート#4:ミンコフスキー時空
- 相対論ノート#5:固有時間と時間の遅れ
- 相対論ノート#6:双子のパラドックスとローレンツ収縮
- 相対論ノート#7:4元速度と4元運動量
- 相対論ノート#8:保存カレントと保存チャージ
- 相対論ノート#9:エネルギーと運動量テンソル
- 相対論ノート#10:等価原理と一般相対性原理
- 相対論ノート#11:リーマン幾何学の基礎
- 相対論ノート#12:スカラー、ベクトル、テンソルの変換則
- 相対論ノート#13:テンソルの縮約と普遍性
- 相対論ノート#14:計量テンソル
- 相対論ノート#15:測地線とクリストッフェル記号
- 相対論ノート#16:共変微分とリーマン距離率テンソル
- 相対論ノート#17:リッチテンソル、アインシュタインテンソル、そしてアインシュタイン方程式
- 相対論ノート#18:アフィン接続係数と座標変換則
- 相対論ノート#19:等価原理とアフィン接続係数
- 相対論ノート#20:ベクトルの平行移動とテンソルの平行移動
- 相対論ノート#21:共変微分
- 相対論ノート#22:共変微分の性質
- 相対論ノート#23:共変微分の発散
- 相対論ノート#24:リーマン曲率テンソルの定義
- 相対論ノート#25:リーマン曲率テンソルの幾何学的意味
- 相対論ノート#26:リーマン曲率テンソルの対称性
- 相対論ノート#27:リッチテンソルとアインシュタインテンソルの導出
- 相対論ノート#28:アインシュタイン方程式の厳密解:シュワルツシルト解
- 相対論ノート#29:重力レンズ効果
- 【補足】ビアンキ恒等式とアインシュタインテンソル – 第30回
- 【補足】弱い重力場中の粒子の運動 – 第31回
- 【補足】重力による時間の遅れと重力赤方偏移 – 第32回
- 【補足】水星の近日点移動の現象 – 第33回
- 【補足】タキオン – 第34回
- 【補足】重力波 – 第35回

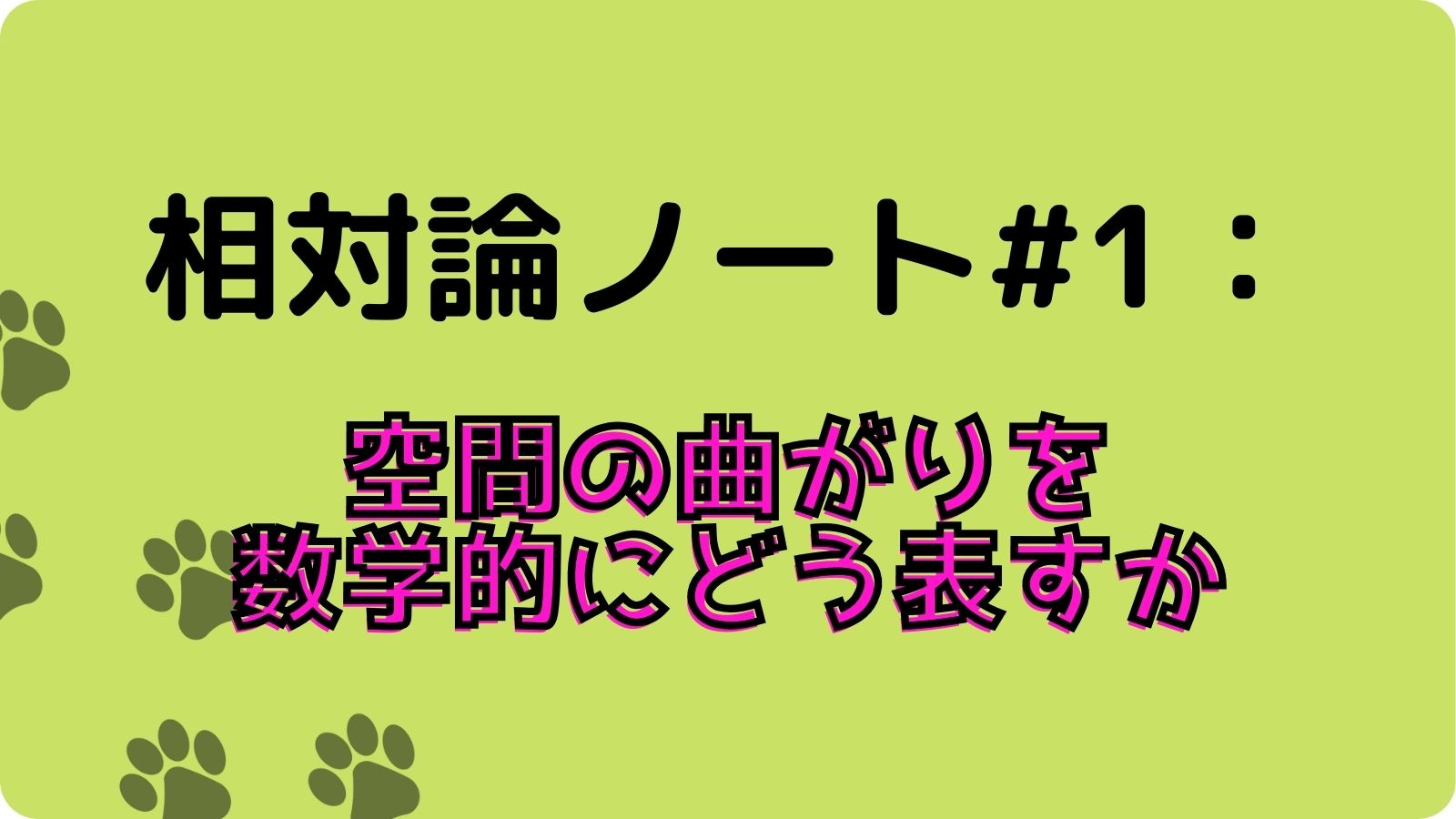


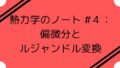
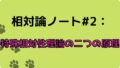
コメント