相対論ノートの第三回です。前回は、特殊相対性理論の二つの柱である「相対性原理」と「光速度不変の原理」についてお話しました。今回は、これらの原理から導き出される重要な座標変換式、「ローレンツ変換」について解説していきます。
ローレンツ変換は、ニュートン力学における「ガリレイ変換」に代わるもので、異なる慣性系間の時間と空間の関係を正確に記述するためのものです。この変換式を理解することで、時間と空間が観測者によって相対的に変化するという、特殊相対性理論の驚くべき結論へとたどり着くことができます。
ローレンツ変換の導出
ローレンツ変換は、特殊相対性理論の二つの原理を仮定して、数学的に導き出すことができます。その導出過程を見ていきましょう。
- 座標系の設定: まず、ある静止した座標系$x$と、その座標系に対して速度$v$で$x$軸方向に移動する別の座標系$x’$を設定します。
- 線形変換の仮定: 時間と空間の変換式を、ニュートン力学のガリレイ変換を一般化した、線形変換として仮定します。相対性理論では、時間と空間をまとめて扱うため、時間を「光速$c$を掛けた$ct$の形」で表現すると便利です。
- 係数の決定: 「光速度不変の原理」の条件を使って、変換式の係数を決定します。具体的には、どちらの座標系から見ても、光の軌跡は同じになるはずです。
- ローレンツ因子の導出: 最後に、$x’$座標系から$x$座標系を見た場合、速度が$-v$になるという対称性を利用して、未知の係数である「ガンマ($\gamma$)」を決定します。
ローレンツ変換の式とローレンツ因子
これらの手順を経て導出されるローレンツ変換の式は、以下のようになります。
$x’=\gamma(x-vt)$
$y’=y$
$z’=z$
ここで、$\gamma$は「ローレンツ因子」と呼ばれ、以下の式で定義されます。
$\gamma=\frac{1}{\sqrt{(1-\frac{v^2}{c^2})}}$
このローレンツ因子が、特殊相対性理論における時間や空間の変化を決定する鍵となります。
速度$v$が光速$c$に比べて十分に小さい場合、$v²/c²$の項はほぼゼロとなり、$\gamma$はほぼ1になります。この時、ローレンツ変換の式は、ニュートン力学の「ガリレイ変換」に帰着します。
これは、私たちが日常的に経験する低速の世界では、ニュートン力学が有効理論として正しいことを示しています。
しかし、速度が光速に近づくにつれて$v²/c²$の項が大きくなり、$\gamma$は1よりもはるかに大きな値になります。この$\gamma$が1を超えることによって、時間の進みが遅れたり、物体の長さが縮んだりする、といった特殊相対性理論ならではの現象が起こります。これは、次のノートで詳しく解説する予定です。
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。
- 一般相対論入門 改訂版 : [須藤 靖 (著)]
- 第3版 シュッツ 相対論入門 I 特殊相対論 : [江里口 良治 (翻訳), 二間瀬 敏史 (翻訳), Bernard Schutz (著) ]
- 第3版 シュッツ 相対論入門 II 一般相対論: [江里口 良治 (翻訳), 二間瀬 敏史 (翻訳), Bernard Schutz (著)]
- 相対性理論入門講義 (現代物理学入門講義シリーズ 1) [風間 洋一 (著)]
- 基幹講座 物理学 相対論 [田中 貴浩 (著)]
- 時空の幾何学:特殊および一般相対論の数学的基礎[James J. Callahan (著), 樋口 三郎 (翻訳)]
- これならわかる工学部で学ぶ数学 新装版: [千葉 逸人]
-
これまでの相対論ノート一覧
- 相対論ノート#1:空間の曲がりを数学的に表すには
- 相対論ノート#2:特殊相対性理論の二つの原理
- 相対論ノート#3:ローレンツ変換とその導出
- 相対論ノート#4:ミンコフスキー時空
- 相対論ノート#5:固有時間と時間の遅れ
- 相対論ノート#6:双子のパラドックスとローレンツ収縮
- 相対論ノート#7:4元速度と4元運動量
- 相対論ノート#8:保存カレントと保存チャージ
- 相対論ノート#9:エネルギーと運動量テンソル
- 相対論ノート#10:等価原理と一般相対性原理
- 相対論ノート#11:リーマン幾何学の基礎
- 相対論ノート#12:スカラー、ベクトル、テンソルの変換則
- 相対論ノート#13:テンソルの縮約と普遍性
- 相対論ノート#14:計量テンソル
- 相対論ノート#15:測地線とクリストッフェル記号
- 相対論ノート#16:共変微分とリーマン距離率テンソル
- 相対論ノート#17:リッチテンソル、アインシュタインテンソル、そしてアインシュタイン方程式
- 相対論ノート#18:アフィン接続係数と座標変換則
- 相対論ノート#19:等価原理とアフィン接続係数
- 相対論ノート#20:ベクトルの平行移動とテンソルの平行移動
- 相対論ノート#21:共変微分
- 相対論ノート#22:共変微分の性質
- 相対論ノート#23:共変微分の発散
- 相対論ノート#24:リーマン曲率テンソルの定義
- 相対論ノート#25:リーマン曲率テンソルの幾何学的意味
- 相対論ノート#26:リーマン曲率テンソルの対称性
- 相対論ノート#27:リッチテンソルとアインシュタインテンソルの導出
- 相対論ノート#28:アインシュタイン方程式の厳密解:シュワルツシルト解
- 相対論ノート#29:重力レンズ効果
- 【補足】ビアンキ恒等式とアインシュタインテンソル – 第30回
- 【補足】弱い重力場中の粒子の運動 – 第31回
- 【補足】重力による時間の遅れと重力赤方偏移 – 第32回
- 【補足】水星の近日点移動の現象 – 第33回
- 【補足】タキオン – 第34回
- 【補足】重力波 – 第35回

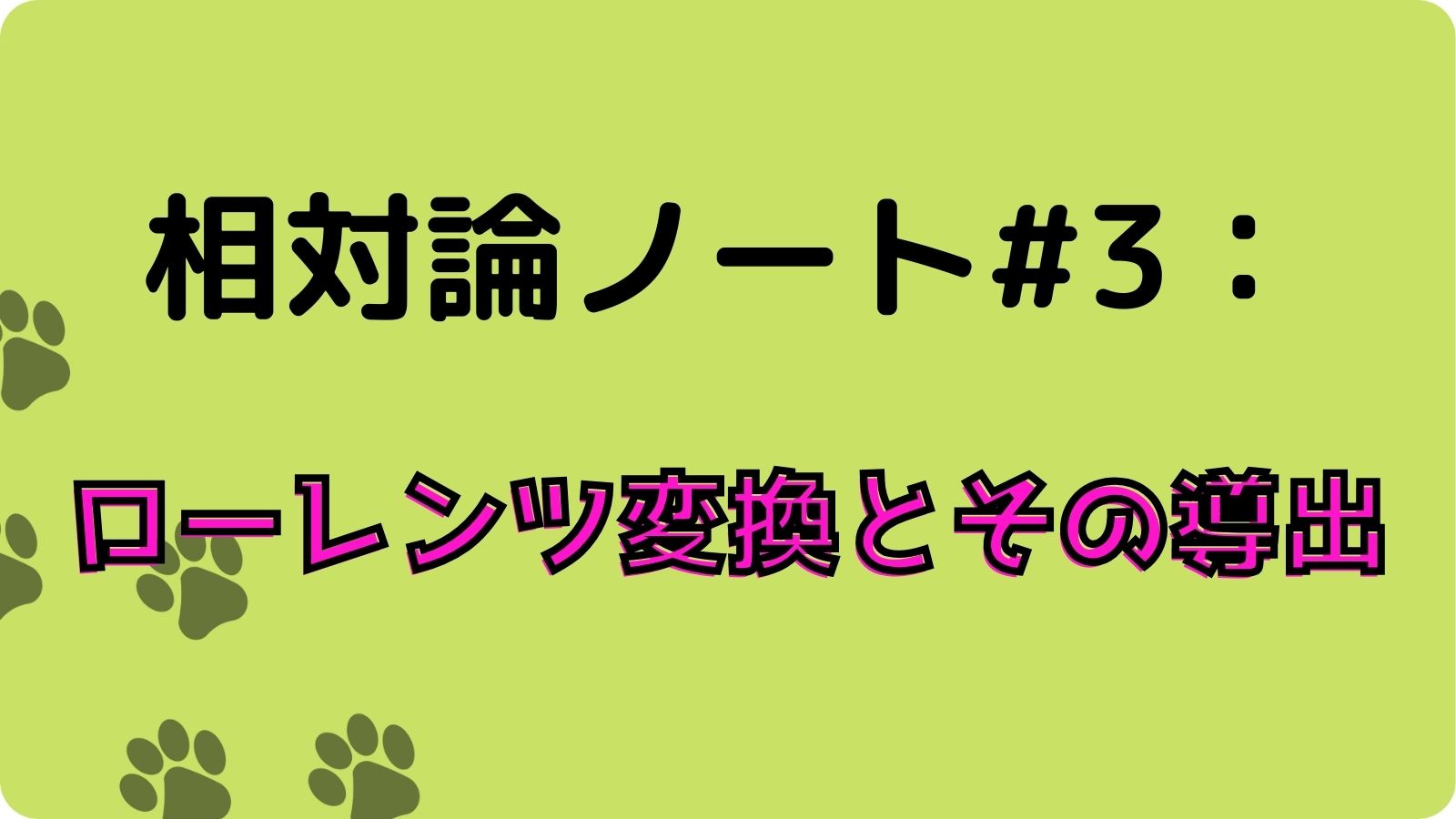


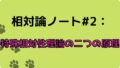
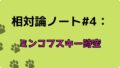
コメント