3/5
物理の全体像:次元の考察と重力のモデル化
前回は、光速が不変であるという原則から、時間と空間が相対的であること、そして4次元時空の概念が生まれたことについて振り返りました。今回は、私たちが住む世界の次元と、重力をどのようにモデル化するのかという話に進んでいきます。なぜ私たちは3次元に住んでいるのか?
私たちの世界はなぜ3次元だとわかるのでしょうか。いくつかの理由が考えられます。- クーロンの法則:電荷間に働く力は、距離の2乗に反比例します。これは、電気力線が3次元空間の球の表面積($4\pi r^2$)に比例して広がっていくためです。もし私たちがn次元に住んでいるなら、この法則は距離の(n-1)乗に反比例するはずなので、距離の逆2乗の法則は3次元の証拠の一つと言えます。
- トポロジー的な考察:数学的な視点からも、2次元ではないことがわかります。たとえば、「ちくわ」のような筒状の物体は、2次元空間では存在できません。また、メビウスの輪やクラインの壺といった図形も、それらを紙から浮かび上がらせる(つまり次元を追加する)ことでしか作れません。私たちがそのような物体を作ったり、認識したりできるのは、少なくとも3次元以上の空間に住んでいる証拠です。
高次元の可能性:コンパクト化とブレーン
一方で、私たちが認識できないだけで、4次元以上の空間が存在する可能性も議論されています。 例えば、紙は普通は2次元の平面に見えるはずですが、筒状に細く限界まで丸めてしまえば1次元の線に見えることがわかります。 同様に、非常に小さなスケールで、我々が認識できない余剰次元が丸まっている(コンパクト化している)可能性があると考えられています。また、私たちはまるで「膜」(ブレーン)のような3次元空間に閉じ込められており、高次元空間を認識できていない可能性も提唱されています。 参考:(備忘録)⑩超弦理論における高次元とコンパクト化重力のモデル化:滑らかな時空
次に、アインシュタインの一般相対性理論が、どのように重力をモデル化しているかについてです。重力には、次のような不思議な性質があります。- 局所的に消せる:自由落下しているエレベーターの中では、物体が浮いて重力が消えたかのように感じます。これを等価原理と呼び、重力と加速度運動が区別できないという考え方です。
- 大局的には消せない:しかし、広い宇宙全体を見ると、重力は消えません。少し曖昧ですが、範囲を広げて自由落下しているエレベータがもう一つあると仮定しましょう。そうすればお互いが観測し合って落ちていることを認識できてしまえる…みたいなものでしょうか?
宇宙のシミュレーション:経路積分
このような理論から導かれる宇宙の形や次元のモデルが妥当であるかを検証するために、シミュレーションが行われます。 この際に使われる重要な手法の一つが、経路積分です。これは、ある状態から別の状態に変化する「すべての可能な経路」を足し合わせることで、最終的な物理現象を予測するというものです。 今回は、私たちが住む世界の次元と、重力の幾何学的なモデルについてまとめました。次回は、この重力のモデルを数学的に表した「アインシュタイン方程式」と、その解から予言された「ブラックホール」について見ていきます。全記事一覧
- 物理の全体像:運動方程式から保存則へ
- 物理の全体像:相対性理論と時空の歪み
- 物理の全体像:次元の考察と重力のモデル化 (今ココ)
- 物理の全体像:アインシュタイン方程式とブラックホール
- 物理の全体像:量子力学と未来の物理学

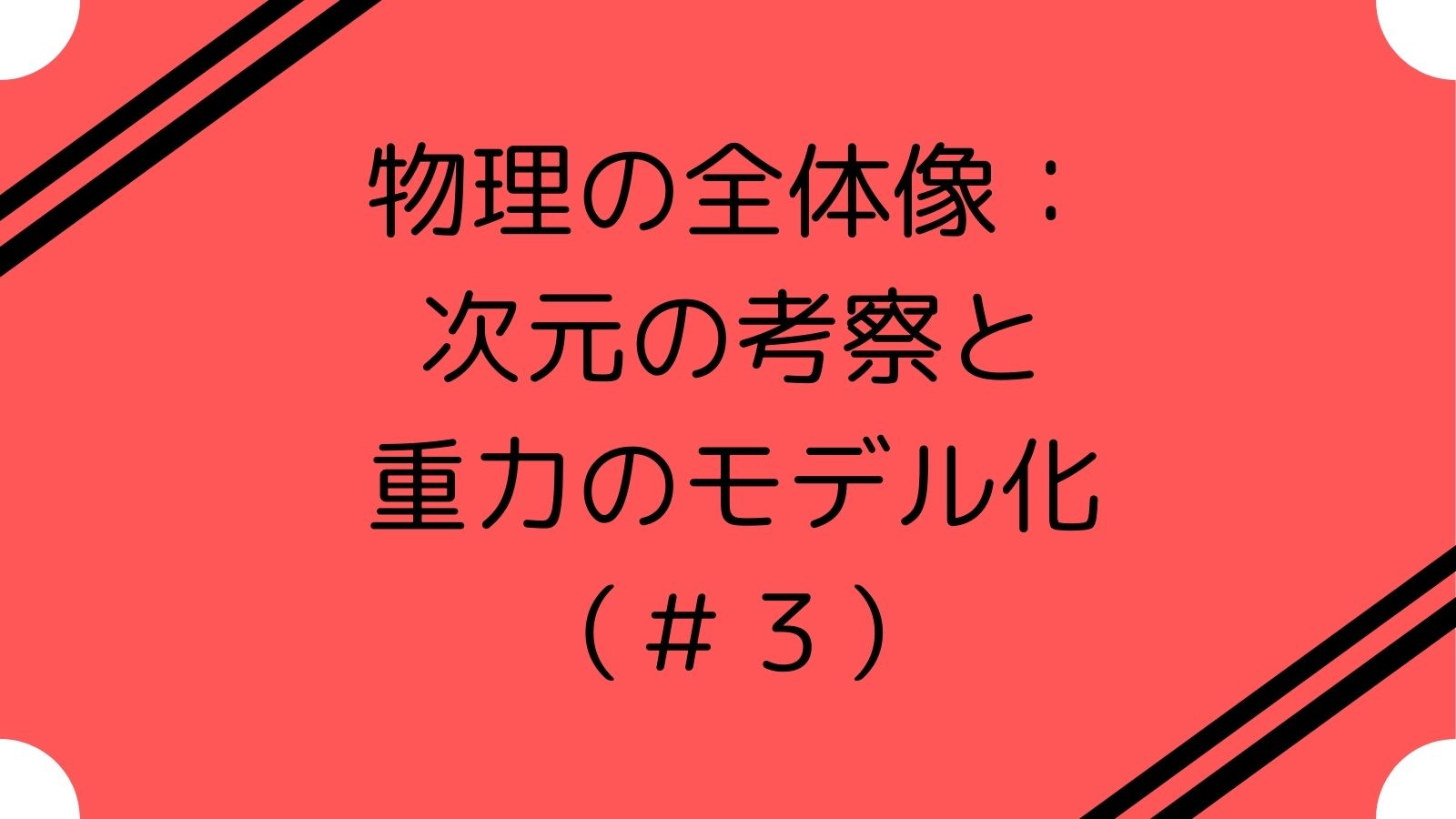


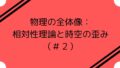
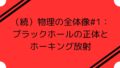
コメント