理想の物体「剛体」の運動方程式
これまで、質点(大きさがなく、質量だけを持つ点)の運動を中心に、古典力学の様々な概念を学んできました。しかし、私たちの身の回りにある物体のほとんどは、大きさを持っていて、しかも形が変わらないわけではありません。
そこで今回は、古典力学の総まとめのようなテーマとして、「剛体(ごうたい)」という、より現実の物体に近い理想的なモデルの運動方程式についてまとめてみました。
剛体とは?
まず、剛体とは何でしょうか。剛体とは、大きさを持ち、どのような力を加えても変形しない、理想的な物体と定義されます。
現実の世界には、完全に変形しない物体は存在しませんが、ビリヤードの球や鉄の棒のように、加える力が十分に小さい限りはほとんど変形しない硬い物体は、剛体とみなしてその運動を議論できる例は多くあります。
この剛体の概念は、物理学や工学の様々な分野で非常に重要な役割を果たしています。
剛体の運動は、大きく分けて二つの種類の運動の組み合わせとして考えることができます。
一つは、全体が平行に動く「並進運動」、もう一つは、ある軸を中心に回転する「回転運動」です。それぞれの運動について、運動方程式を導出してみましょう。
剛体の並進運動方程式
剛体の並進運動方程式は、意外にもシンプルで、質点の運動方程式と似た形になります。
導出の考え方は、「剛体は、たくさんの小さな質点の集まりである」とみなすことです。
剛体内の$N$個の質点$i$(質量$m_i$、位置ベクトル$r_i$)について、それぞれ運動方程式を立ててみましょう。
$$m_i \frac{d^2r_i}{dt^2} = F_i$$
ここで、$F_i$は質点$i$に働く力です。この力$F_i$は、剛体の外から質点$i$に直接働く「外力」$F_i^{\text{ext}}$と、剛体内の他の質点から質点$i$に働く「内力」$F_i^{\text{int}}$に分けることができます。
$$m_i \frac{d^2r_i}{dt^2} = F_i^{\text{ext}} + F_i^{\text{int}}$$
次に、剛体全体の運動を考えるために、これらの運動方程式をすべての質点について足し合わせます。
$$\sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d^2r_i}{dt^2} = \sum_{i=1}^{N} F_i^{\text{ext}} + \sum_{i=1}^{N} F_i^{\text{int}}$$
ここで重要なのが、ニュートンの第三法則「作用・反作用の法則」です。これにより、剛体内の質点同士が及ぼし合う内力は、互いに打ち消し合うため、内力の合計はゼロになります。
$$\sum_{i=1}^{N} F_i^{\text{int}} = 0$$
したがって、式は次のようになります。
$$\sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d^2r_i}{dt^2} = \sum_{i=1}^{N} F_i^{\text{ext}}$$
左辺について、剛体の重心$R$の位置を定義します。重心は、次の式で表されます。
$$R = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i r_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i}$$
ここで、$\sum_{i=1}^{N} m_i$は剛体全体の質量$M$なので、
$$MR = \sum_{i=1}^{N} m_i r_i$$
この式の両辺を時間で二回微分すると、
$$M \frac{d^2R}{dt^2} = \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d^2r_i}{dt^2}$$
となります。したがって、剛体の並進運動方程式は、最終的に次の形にまとまるようです。
$$M \frac{d^2R}{dt^2} = \sum_{i=1}^{N} F_i^{\text{ext}}$$
この式は、「剛体全体の質量に、重心の加速度を掛けたものが、剛体に働く外力の合計に等しい」ということを意味しています。
これは、まるで剛体全体の質量が重心に集中し、すべての外力が重心に作用しているかのように考えてよい、ということを示唆しています。これは、剛体の並進運動を質点と同じように扱える、という点で非常に便利な結果だと思います。
剛体の回転運動方程式
次に、剛体の回転運動方程式です。こちらは並進運動方程式よりも少し複雑になります。
並進運動と同様に、剛体を質点の集まりとみなします。各質点$i$の回転に関する運動は、前回学んだ角運動量とトルクの関係で記述できそうですね。
質点$i$に働くトルク$N_i$は、その質点の位置$r_i$と、質点に働く力$F_i$のベクトル積で表されました。
$$N_i = r_i \times F_i = r_i \times \frac{dp_i}{dt}$$
そして、このトルクが質点$i$の角運動量$L_i$の時間変化に等しい、という関係がありました。
$$N_i = \frac{dL_i}{dt}$$
ここで、$L_i = r_i \times p_i$です。
剛体全体の回転運動を考えるために、すべての質点についてこれらの式を足し合わせます。
$$\sum_{i=1}^{N} N_i = \sum_{i=1}^{N} \frac{dL_i}{dt}$$
左辺のトルク$N_i$も、外力によるトルク$N_i^{\text{ext}} = r_i \times F_i^{\text{ext}}$と、内力によるトルク$N_i^{\text{int}} = r_i \times F_i^{\text{int}}$に分けることができます。
$$\sum_{i=1}^{N} (N_i^{\text{ext}} + N_i^{\text{int}}) = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^{N} L_i\right)$$
ここでも、作用・反作用の法則が活躍します。剛体内の内力は互いに打ち消し合うだけでなく、内力によるモーメント(トルク)の合計もゼロになる、という性質があります。これは、剛体であるという性質(質点間の距離が変わらない)から導かれる重要な結論です。
$$\sum_{i=1}^{N} N_i^{\text{int}} = 0$$
したがって、剛体の回転運動方程式は、次の形になります。
$$\sum_{i=1}^{N} N_i^{\text{ext}} = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^{N} L_i\right)$$
ここで、左辺は剛体に働く外力による全トルク$N_{\text{total}}^{\text{ext}}$、右辺は剛体全体の全角運動量$L_{\text{total}}$の時間微分です。
$$N_{\text{total}}^{\text{ext}} = \frac{dL_{\text{total}}}{dt}$$
この式は、「剛体に働く外力による全トルクは、剛体全体の全角運動量の時間変化に等しい」ということを示しています。これは、質点の運動量と力積の関係の、回転運動バージョンだと考えることができるかもしれません。
この議論は、質点が離散的に$N$個集まっている場合の話でしたが、剛体は実際には連続的な物体です。そこで、離散的な「和」($\sum$)を「積分」($\int$)に置き換えることで、連続的な剛体にも適用できるようになります。
まとめ
今回は、剛体の運動方程式についてまとめてみました。
剛体を質点の集まりと考えることで、並進運動と回転運動のそれぞれについて、運動方程式が導出できることについて書きました。特に、並進運動が重心の運動として記述できる点や、回転運動が全角運動量の時間変化として記述できる点は、楽しい結果だと感じます。
この剛体の運動方程式は、機械の設計や天体の運動の解析など、現実世界で非常に幅広く応用されています。
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。
古典力学ノート シリーズ一覧
- 古典力学ノート #1:ニュートン力学の基本原理とエネルギーの概念について
- 古典力学ノート #2:運動量と力積、そして運動量保存則について
- 古典力学ノート #3:回転の勢いを表す「角運動量」について
- 古典力学ノート #4:見かけの力「慣性力」について
- 古典力学ノート #5:回転系に現れる「遠心力」と「コリオリ力」
- 古典力学ノート #6:理想の物体「剛体」の運動方程式
- 古典力学ノート #7:回転のしにくさを表す「慣性モーメント」

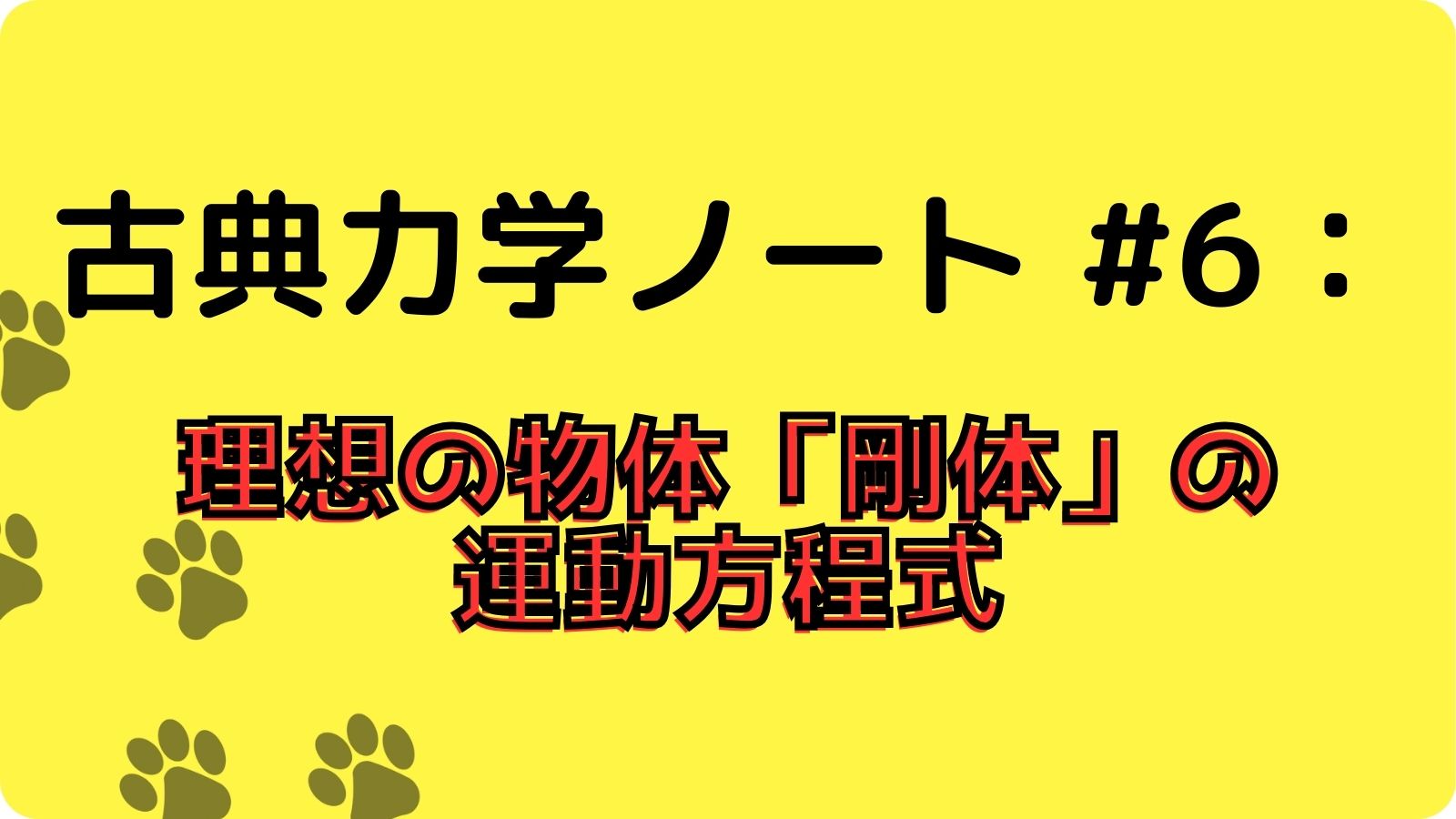


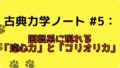
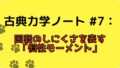
コメントを残す