回転系に現れる「遠心力」と「コリオリ力」
前回は、電車が急ブレーキをかけたときのような、並進運動(直線的な加速)をする座標系で現れる「慣性力」についてまとめてみました。
今回は、さらに複雑な「回転運動」をする座標系に現れる、少し不思議な慣性力について触れてみたいと思います。バケツを振り回したときに感じる力や、台風の渦ができる原因も、この慣性力で説明できるようです。
回転系に現れる3つの慣性力
回転する座標系では、大きく分けて3種類の慣性力が見かけ上、現れます。
おそらく、一番なじみのある慣性力かもしれません。遠心力は、回転の中心から外向きに働くように見える力です。
例えば、バケツに水を入れて振り回しても、水がこぼれない現象が例として挙げられるかと思います。これは、水に遠心力が働き、バケツの底に押し付けられているからだと説明できます。
コリオリ力は、少し理解が難しい慣性力かもしれません。物体の運動方向に対して垂直な方向に働くように見える力です。
例えば、人工的な宇宙コロニーのような回転する居住スペースの中で、真下にボールを落とすと、ボールは少し横にずれて落下するそうです。この横向きのずれの原因が、コリオリ力だと言われています。地球上でも、大気の流れや海流、そして台風の渦にも影響を与えています。
これは、回転系の角速度が時間的に変化する場合に現れる慣性力です。回転の勢いが速くなったり遅くなったりするような状況で、初めて現れる慣性力で、遠心力やコリオリ力に比べると、日常ではあまり意識しないかもしれません。
回転系における運動方程式の導出
これらの慣性力がなぜ現れるのか、数式を追って考えてみます。
まず、二つの座標系を設定します。一つは静止した「慣性系」、もう一つは慣性系に対して回転している「回転系」です。
慣性系での物理量(位置、速度、加速度)には添え字をつけず、回転系での物理量には「’」をつけて区別します。
物理量を変換するためのキーとなるのが、時間微分の関係式です。慣性系と回転系でベクトルを時間微分するときの関係は、回転の角速度を$\omega $とすると、次のようになります。
$$\left(\frac{d \cdot}{dt}\right)_{\text{慣性}} = \left(\frac{d \cdot}{dt}\right)_{\text{回転}} + \omega \times \cdot$$
この式は、慣性系での時間微分は、回転系での時間微分に、回転による余分な項を加えたものに等しい、ということを示しています。
この関係式を使って、まず慣性系での速度$v$と回転系での速度$v’$の関係を導出してみます。位置ベクトル$\vec{r}$を時間微分すると、
$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r’}}{dt} + \vec{\omega} \times\vec{ r’ }= \vec{v’} +\vec{ \omega} \times\vec{ r’}$$
となり、慣性系での速度は、回転系での速度と、回転による速度の和に等しい、という関係が導き出されます。
次に、この速度の関係式をもう一度時間微分して、慣性系での加速度$\vec{a}$と回転系での加速度$\vec{a’}$の関係式を導出します。
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{v’} +\vec{ \omega }\times \vec{r’})$$
右辺を時間微分すると、積の微分法則などを使って、いくつかの項が現れます。
$$\vec{a} = \vec{a’} + 2\vec{\omega} \times \vec{v’ }+ \vec{\omega }\times (\vec{\omega} \times \vec{r’}) + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times\vec{ r’}$$
少し複雑な式ですが、これが慣性系と回転系における加速度の関係式です。
最後に、ニュートンの運動方程式$\vec{F} = m\vec{a}$にこの関係式を代入してみます。
$$\vec{F} = m \left(\vec{ a’} + 2\vec{\omega }\times \vec{v’} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega }\times \vec{r’}) + \frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r’} \right)$$
この式を、非慣性系における運動方程式の形に変形します。つまり、$m\vec{a’}$を左辺に持ってくるように整理します。
$$m\vec{a’ }= \vec{F} – m(2\vec{\omega} \times \vec{v’}) – m(\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r’})) – m\left(\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r’}\right)$$
この式は、「回転系で観測される力は、物体に働く実際の力に、いくつかの慣性力が加わったものに見える」ということを示しています。
ここで、右辺の第二項以降が、回転系で現れる慣性力です。
- $-m(\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r’}))$:これが遠心力の項です。ベクトル積の性質から、この力は回転中心から外向きに働くことが示せます。
- $-m(2\vec{\omega} \times \vec{v’})$:これがコリオリ力の項です。物体の速度$v’$に依存し、速度の向きに対して垂直に働くように見えます。
- $-m\left(\frac{d\vec{\omega}}{dt} \times \vec{r’}\right)$:これが、角速度$ \vec{\omega} $が時間的に変化する場合に現れる慣性力です。
これらの慣性力は、すべて座標系の回転による見かけ上の力であり、慣性系では存在しないことが分かります。
まとめ
今回は、少し難易度が上がったように感じましたが、回転系で観測される不思議な力、遠心力やコリオリ力が、座標系の変換から自然に導かれることをまとめました。
これらの知識は、剛体の運動や、惑星の軌道、あるいは宇宙工学のような分野を理解する上で、とても重要なステップになります。
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。
古典力学ノート シリーズ一覧
- 古典力学ノート #1:ニュートン力学の基本原理とエネルギーの概念について
- 古典力学ノート #2:運動量と力積、そして運動量保存則について
- 古典力学ノート #3:回転の勢いを表す「角運動量」について
- 古典力学ノート #4:見かけの力「慣性力」について
- 古典力学ノート #5:回転系に現れる「遠心力」と「コリオリ力」
- 古典力学ノート #6:理想の物体「剛体」の運動方程式
- 古典力学ノート #7:回転のしにくさを表す「慣性モーメント」

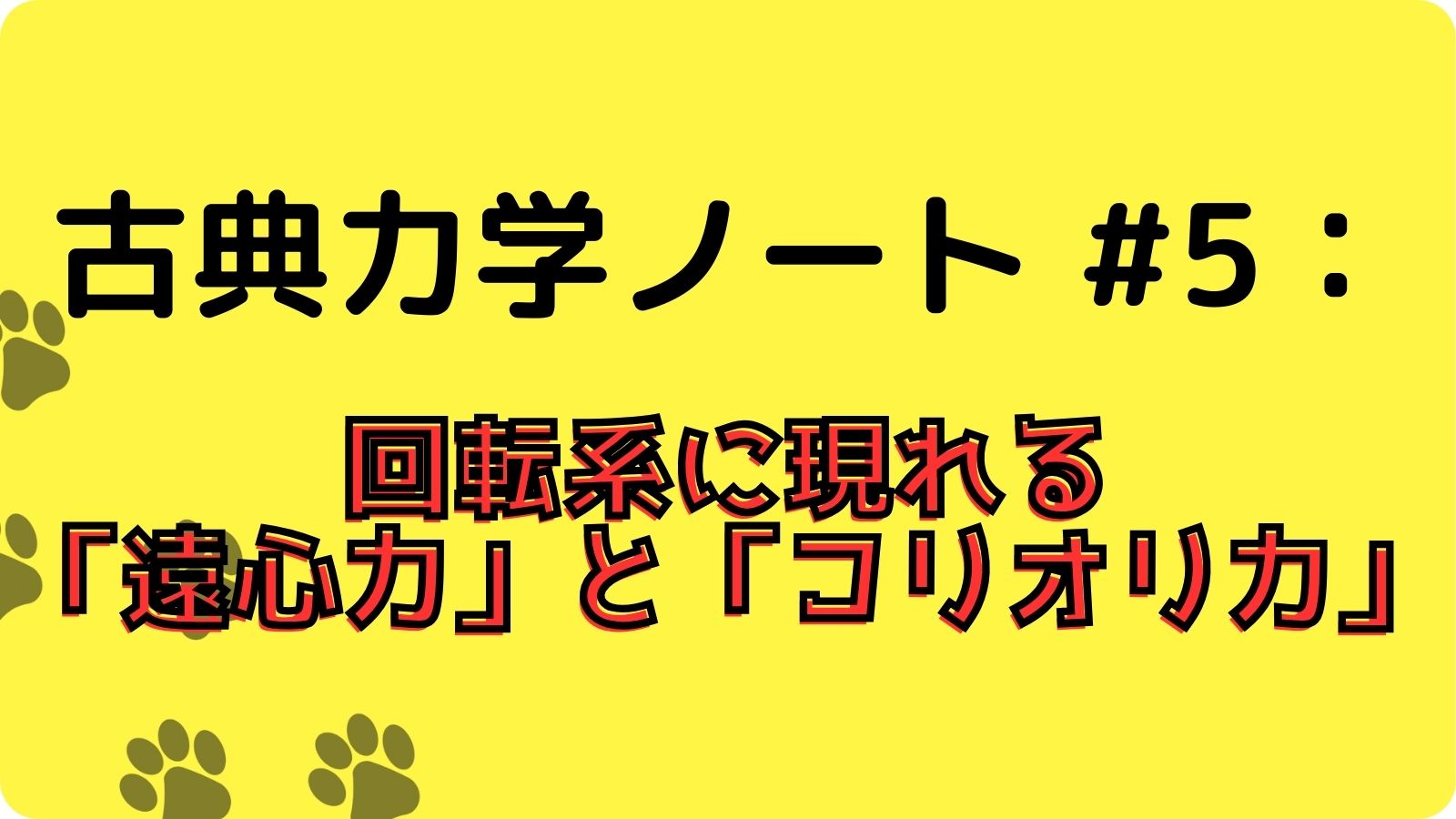


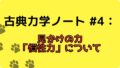
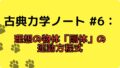
コメントを残す