『勉強会カテゴリー/タグ』についての背景や取扱については”コチラ”をご覧ください.
中学数学の学び直し!第5回:確率と統計の考え方
今回は、データ分析やAIの分野で特に重要な役割を果たす「確率」と「統計」の基礎を解説します。これらは、データから未来を予測したり、傾向を読み解いたりする際に欠かせない考え方です。
1. 確率とは?
中学数学では、「ある事柄がどれくらいの割合で起こるか」を「確率」と呼びました。例えば、サイコロを振って特定の目が出る確率を求めることなどがそうです。
プログラミングでは、ランダムな動作をシミュレーションしたり、*特定のイベントが起こる可能性を計算したりする際に、この確率の考え方を使います。例えば、ゲームでのアイテムのドロップ率や、機械学習における予測結果の信頼度などに応用されます。
この処理をPythonで書くと次の様に書けます。
# Python
import random# 1から6の目があるサイコロを振る
result = random.choice([1, 2, 3, 4, 5, 6])
print(f”出た目は: {result}”)
“`
このように、確率は、不確実な事象を数値で表現するために使われます。
2. 統計とは?
中学数学で習った「平均」や「中央値」といったものは、たくさんのデータから全体の傾向や特徴を読み解くための方法であり、これが「統計」の基礎です。
プログラミングでは、膨大なデータの中から意味のある情報を引き出すために統計が使われます。例えば、あるWebサイトの利用者の年齢層を分析して平均年齢を計算したり、売上が最も多い時間帯を特定したりする際に活用されます。
この処理をPythonで書くと次の様に書けます。
# Python
import numpy as npsales = [100, 150, 120, 200, 180]
# 売上の平均値を計算する
average_sales = np.mean(sales)
print(f”売上の平均値は: {average_sales}”) # 150.0
“`
このように、統計を理解することで、データに基づいた意思決定ができるようになります。
3. まとめと次回予告
今回は、データ分析の基礎である「確率」と「統計」について解説しました。
「確率」は未来を予測するためのツール、「統計」は過去のデータから傾向を読み解くためのツールです。これらの考え方は、データサイエンスや機械学習の分野で、データに基づいた合理的な判断を下すための基礎となります。
次回は、連載のまとめとして、これまでの知識がどのように繋がっているか、そして今後の学習にどう活かしていくかを解説します。お楽しみに!
連載の続きはこちら!

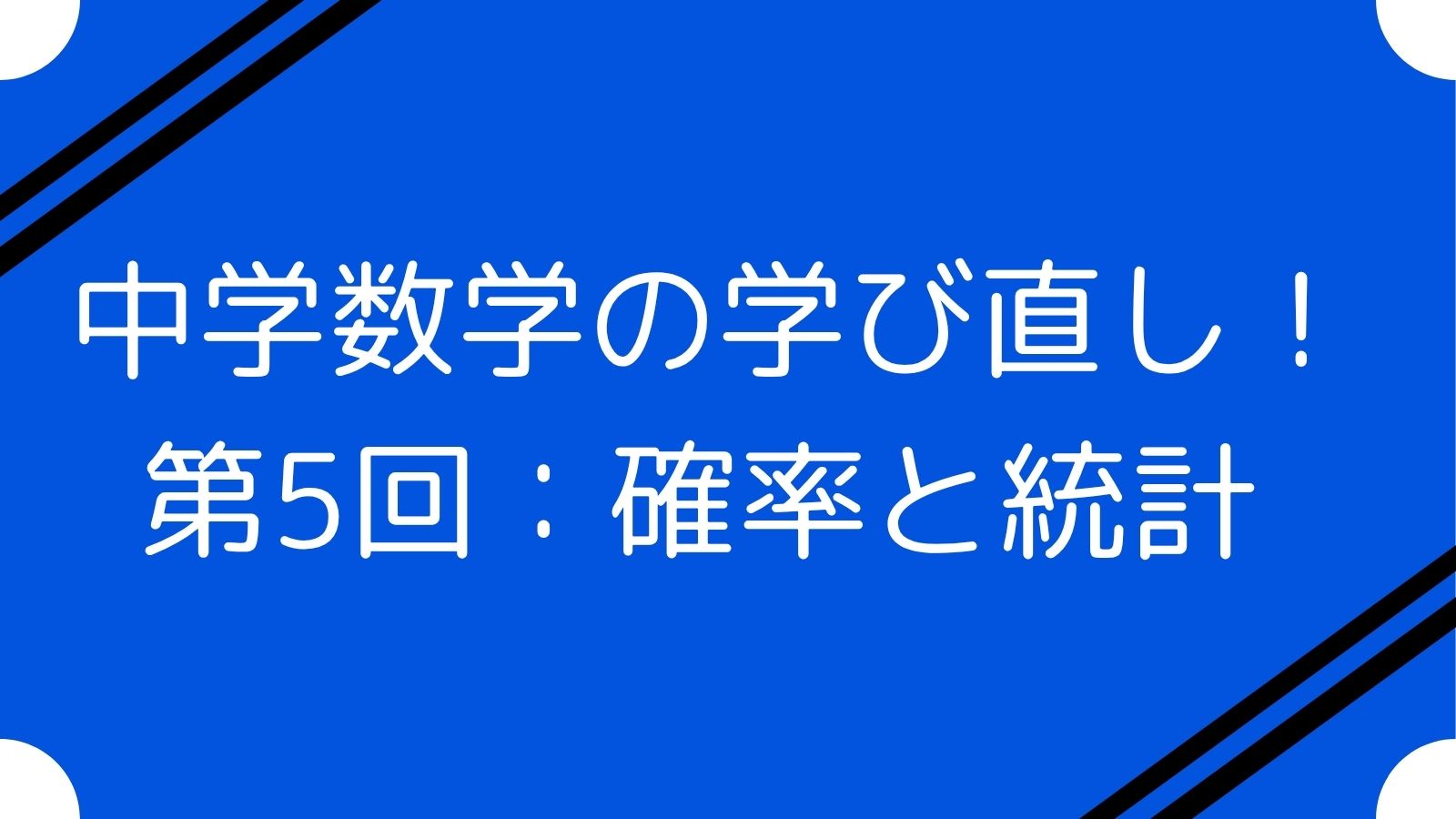



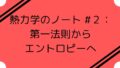
コメント