素人が量子情報に挑んでみた!有志勉強会の記録
先日、有志で集まったネット上の勉強会で、量子情報について語り合いました。私は量子力学の勉強を少ししている程度なので、かなり曖昧な理解だったのですが、熱心な参加者の方に質問をぶつけながら、少しずつ理解を深めていった感じです。当日の議論の内容を思い出しながらまとめてみました。量子コンピュータの「状態」をどうやって表現するのか
量子情報の本を読んだときに、まず驚いたのが、古典コンピュータと量子コンピュータでの「状態」の表し方の違いです。古典コンピュータでは、電流が流れているかどうかで、ONとOFFの2つの状態を表しますよね。それが量子コンピュータでは、粒子の「スピン」の向き、具体的には「上向き」と「下向き」で状態を表現するとのことでした。 古典的なON/OFFとは違って、このスピンの状態はちょっと特殊な振る舞いをします。どうやら、観測するまでは「上向き」と「下向き」の両方の状態が同時に存在している(重ね合わせ)と考えなくてはならないらしいのです。そして、この重ね合わせの状態こそが、量子コンピュータの鍵になる部分だというお話でした。量子コンピュータはなぜ速いのか?
量子コンピュータは「速い」という漠然としたイメージを持っていましたが、これも少し語弊があるそうです。どうやら、古典コンピュータとはアルゴリズムが異なり、特定の課題を選んで適切なアルゴリズムを設定すれば、古典コンピュータよりも圧倒的に速く計算できる、という意味合いらしいです。 その速さの秘密は、先ほどの「重ね合わせ」にあるようです。古典コンピュータが1ビットで1つの状態しか表現できないのに対し、量子コンピュータは1つの量子ビット(キュービット)で、ONとOFFの重ね合わせの状態を表現できます。キュービットの数が増えると、この重ね合わせの数が指数関数的に増えていくとのこと。例えば、50個のキュービットがあれば、およそ1000兆通りの情報を同時に扱える可能性があるという話でした。 これは、古典コンピュータが膨大な回数の計算を必要とするような問題でも、量子コンピュータならごく少ない回数で解ける可能性があることを意味するようです。例えば、$N$通りのパターンを探索する問題では、古典コンピュータが$N$回の計算を要するのに対し、量子コンピュータでは$\sqrt{N}$回程度で済むアルゴリズム(グローバーのアルゴリズムというらしいです)が存在するそうです。この指数関数的な情報量の増加が、量子コンピュータの最大の強みなのかもしれません。一番の不思議「エンタングルメント(量子もつれ)」
一番議論が白熱したのが、エンタングルメントという現象です。これは、2つの量子が絡み合った状態のことらしいのですが、不思議なのは、どれだけ遠く離れていても、片方の量子の状態が確定すると、もう片方の状態も瞬時に確定してしまうという現象です。 相対性理論では、どんな情報も光速を超えられないはずなのに、これは矛盾しないのか?という疑問がわいてきました。勉強会では、「この現象は情報の伝達には使えないから矛盾しない」という解説がありました。なぜかというと、片方の量子の状態がどちらに確定するかはランダムなので、観測者はその結果を制御できないからです。結果を相手に伝えるには、結局電話やメールなど、光速を超えられない手段を使うしかないとのことでした。 ただ、この性質はセキュリティに応用できる可能性があるそうです。もし盗聴者がいた場合、アリスとボブの間にあるエンタングルメントの状態が乱れるため、それを検知することで盗聴を阻止できるかもしれない、という話はとてもワクワクしました。身近な製品にも潜む量子力学
コーヒーブレイク的な話で、とても面白かったのが、同じ製造過程で作られたパソコンでも性能にばらつきが出ることがある、という話でした。これは、半導体チップの内部では、原子数十個という非常に小さなスケールで量子力学の効果が無視できなくなるからだそうです。不純物原子の配置の不確実性や、トンネル効果によって意図しない電流が流れたりすることが、性能のばらつきにつながるそうです。 この量子力学的なばらつきは、完全に防ぐことはできないとのことでした。性能のばらつきが小さければ製品として出荷され、極端なばらつきが出たものが初期不良品として扱われることもあるそうです。普段、同じ製品を買っても性能が違うということを意識したことはありませんでしたが、そんなミクロな世界で物理現象が影響していると知って、なんだかロマンを感じました。
余談:ブラックホールとの関係?
エンタングルメントの話のときに、「光ですら抜け出せないブラックホールの内部も、もしかしたら観測できるのではないか?」という素人考えを口にしたのですが、これもできないとのことでした。なぜなら、エンタングルメントによる相関自体が、ブラックホール内部の具体的な情報を外部に伝えるわけではないからです。量子力学は本当に奥が深いですね。
用語集(超ざっくり解説)
- 量子力学
- 原子や電子といった、非常に小さな粒子の振る舞いを記述する物理学の理論。私たちの日常の感覚とは異なる、不思議な現象を扱います。
- 重ね合わせの原理
- 量子が、観測されるまで複数の状態を同時に持っているという考え方。例えば、箱の中の猫が「生きている」と「死んでいる」の両方の状態を同時に持っているという思考実験が有名です。
- 不確定性原理
- 粒子の位置と運動量など、特定のペアになる物理量を同時に正確に知ることはできないという原理。片方を正確に測ろうとすると、もう片方が不確かになります。
- 量子ビット(キュービット)
- 量子コンピュータが扱う情報の最小単位。古典コンピュータのビット(0か1)とは違い、重ね合わせの状態を取ることができます。
- エンタングルメント(量子もつれ)
- 複数の量子が、お互いの状態が相関し合った状態のこと。たとえ遠く離れていても、片方の状態を観測すると、もう片方の状態も瞬時に確定します。
※本記事は、筆者の記憶に基づく内容であり、正確性や専門性を保証するものではありません。ご意見やご指摘がありましたら、ぜひお聞かせください。
参考文献
記事を書くときに、参照したので載せておきます。- 入門 現代の量子力学 量子情報・量子測定を中心として (KS物理専門書): [堀田 昌寛 (著)]
- 量子コンピュータ―超並列計算のからくり (ブルーバックス): [竹内 繁樹 (著)]
- 今度こそわかる量子コンピューター (今度こそわかるシリーズ): [西野友年 (著) ]
- ブラックホールと時空の方程式:15歳からの一般相対論 : [小林 晋平 (著)]
- 宇宙の見え方が変わる物理学入門 : [小林 晋平 (著)]
- 宇宙を動かす力は何か 日常から観る物理の話 (新潮新書) : [松浦 壮 (著)]
- 時間とはなんだろう 最新物理学で探る「時」の正体 (ブルーバックス)[松浦壮 (著) ]
- 量子とはなんだろう 宇宙を支配する究極のしくみ (ブルーバックス) [松浦壮 (著) ]

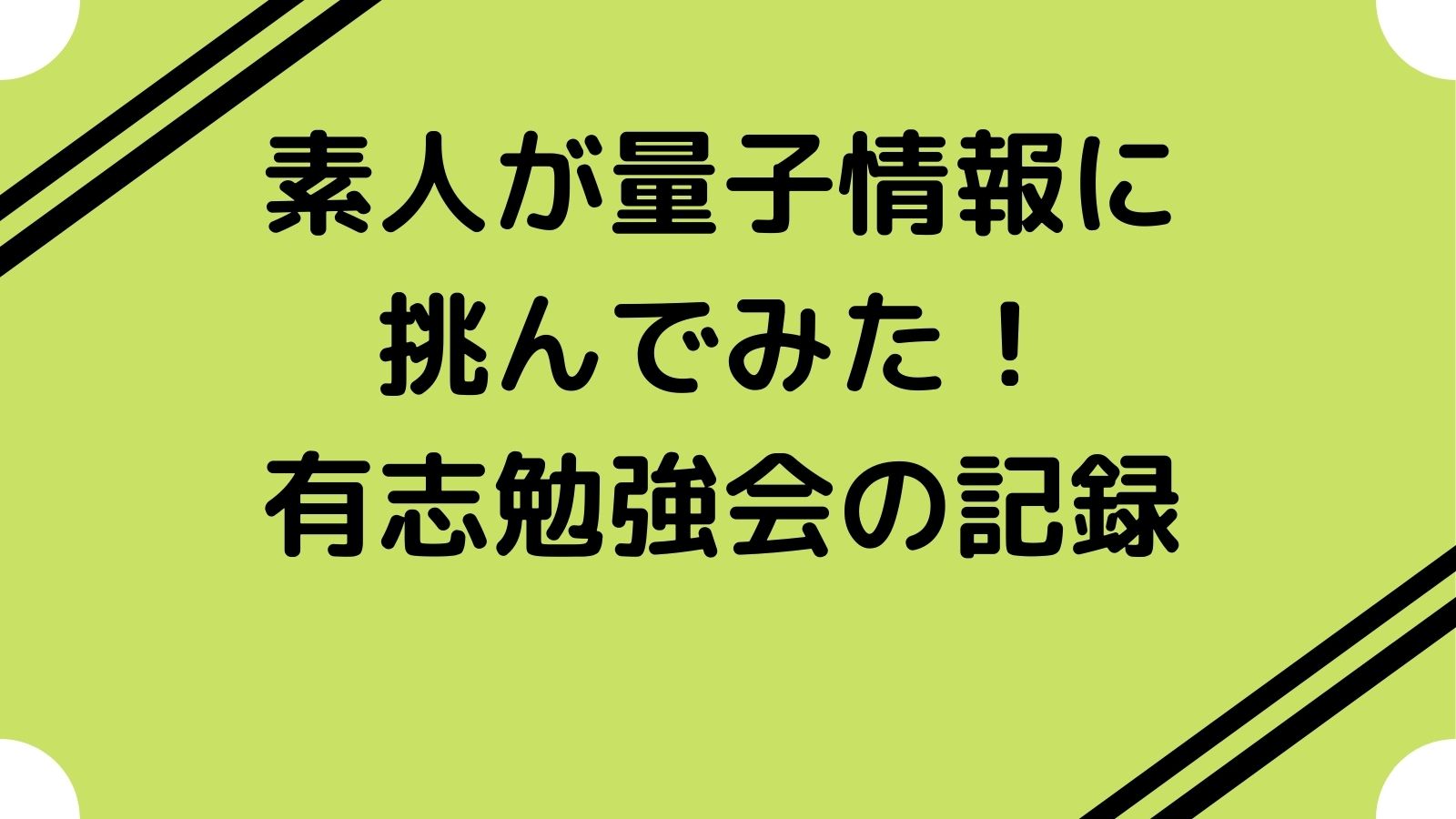


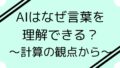
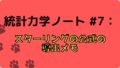
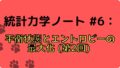
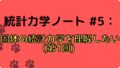
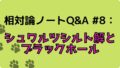
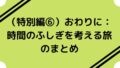
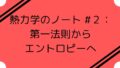
コメント