『勉強会カテゴリー/タグ』についての背景や取扱については”コチラ”をご覧ください.
中学数学の学び直し!第4回:連立方程式と行列の考え方
1. 連立方程式とは?
中学数学では、2つ以上の文字(変数)を含む方程式を組み合わせ、「すべての式を満たす文字の値を求めること」を「連立方程式」と呼びました。
$x + y = 5$
$x − y = 1$
という2つの式を同時に満たす$x$と$y$の値を求めることですね。連立方程式を解くことで、$x = 3, y = 2$という答えが導き出されます。
この考え方は、複雑な条件が絡み合うプログラムで、複数の変数の最適な値を導き出す際に役立ちます。
2. 行列とは?
数学では「行列」という概念があります。数字を縦と横に並べたものです。プログラミング、特にデータサイエンスや機械学習の分野では、この行列が多用されます。
例えば、$x + y = 5$と$x − y = 1$の連立方程式は行列の形で書き表すことができます。
\[
\begin{pmatrix}
1 & 1 \\
1 & -1
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
x \\
y
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
5 \\
1
\end{pmatrix}
\]
以上のように、行列を使うことで、複数のデータをまとめて、一度に効率よく計算できるようになります。AIや画像処理では、膨大なデータをこの行列に変換して処理を行うのが一般的です。
例えば、この処理をPythonで書くと次の様に書けます。
# Python
import numpy as np# 連立方程式の係数を行列で表す
A = np.array([[1, 1], [1, -1]])
# 結果のベクトル
b = np.array([5, 1])# 連立方程式を解く
x = np.linalg.solve(A, b)
print(x) # [3. 2.]
“`
このように、行列を理解することで、より高度なアルゴリズムやデータ処理の仕組みが理解できるようになります。
3. まとめと次回予告
今回は、複数の変数を扱うための「連立方程式」と、その応用である「行列」について解説しました。
「連立方程式」は複雑な条件から答えを導くためのツール、「行列」は大量のデータを効率的に処理するための箱です。これらの考え方は、AIやデータ分析の基礎となります。
次回は、プログラムで欠かせない「確率」と「統計」について解説します。お楽しみに!
連載の続きはこちら!

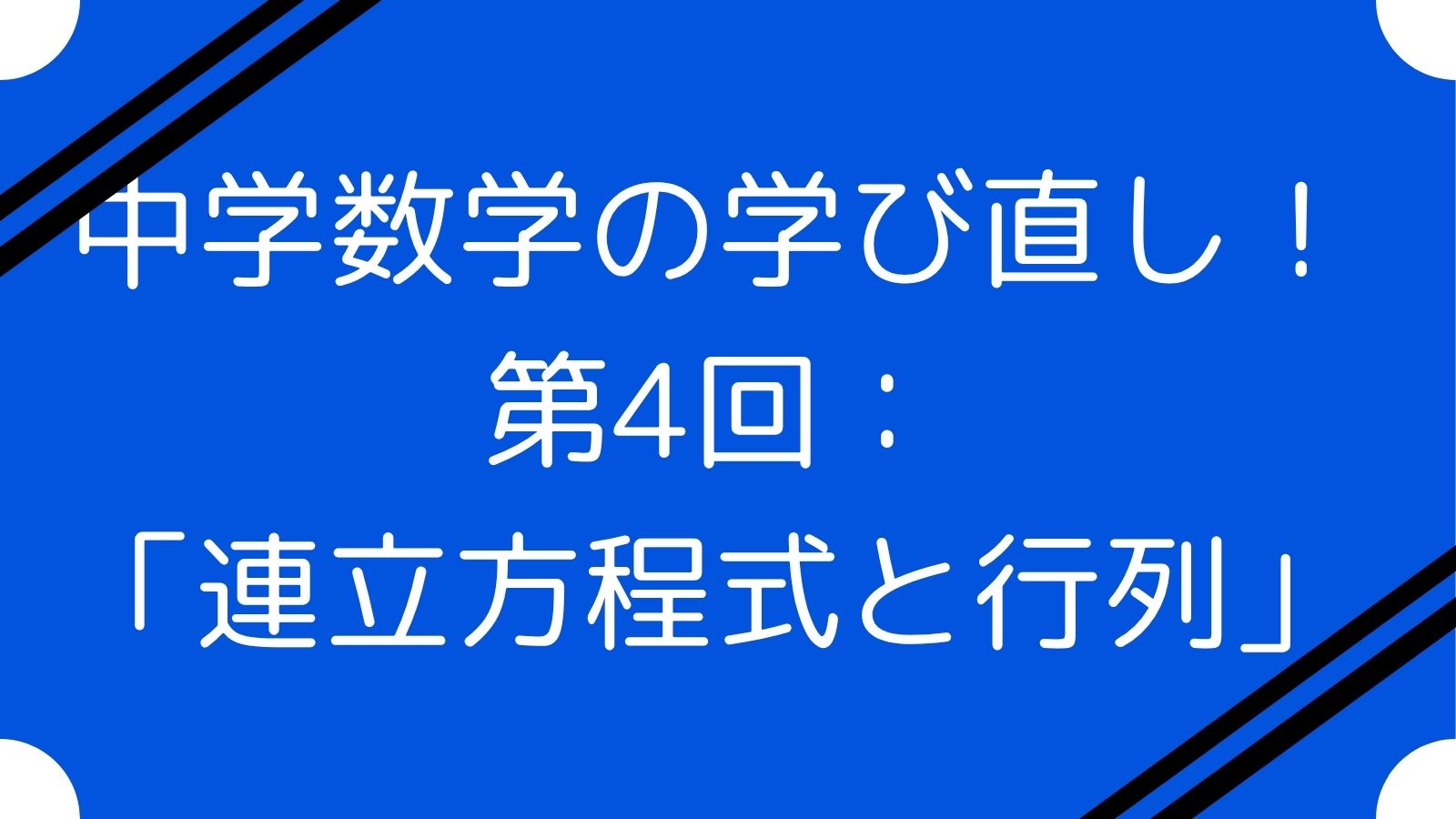



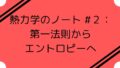
コメント