見かけの力「慣性力」について
これまで、ニュートンの運動方程式や、運動量、エネルギーといった古典力学の基本的な概念について触れてきました。これらはすべて、ニュートンの第一法則が成り立つ特別な座標系、「慣性系」を前提に考えられていました。
しかし、私たちの日常には、電車が急ブレーキをかけたときや、カーブを曲がるときに感じる、あの「体を押されるような力」のように、どうも説明しきれない力があるように感じます。
実は、これらの力は慣性系では存在しないのですが、「非慣性系」という、加速している座標系で運動を記述しようとしたときに、見かけ上現れる力です。今回は、その「慣性力」について、まとめていきます。
慣性力の正体
慣性力は、実際に何かの物体が押しているわけではなく、座標系の加速度によって生じる「見かけの力」です。この見かけの力がなぜ現れるのか、二つの異なる座標系を設定して考えてみます。
まず、ニュートンの法則が成り立つ静止した「慣性系」の座標を$X$とします。
次に、慣性系に対して加速している「非慣性系」の座標を$X’$とします。
そして、慣性系の原点から見た非慣性系の原点の位置ベクトルを$X_0(t)$とします。
ちなみに、加速度が生じない状況ならば”慣性系”とみなせるため、座標$X$自体が等速直線運動している場合でも同じように考えることができます。ただし、その場合は常に速度$v$で動いているので、その分だけ式に項が加わります。
これらの関係は、慣性系から見た物体の位置$X$は、非慣性系から見た物体の位置$X’$と、非慣性系の原点の位置$X_0(t)$の和に等しくなる、と考えることができます。
$$X = X’ + X_0(t)$$
この式は、それぞれの座標系から見た位置の関係を示しています。
慣性力の導出
次に、この式を時間で二回微分して、それぞれの座標系における加速度の関係を見てみましょう。
$$\frac{d^{2} X}{dt^2} = \frac{d^{2} X’}{dt^2} + \frac{d^{2} X_0(t)}{dt^2}$$
ここで、$ \frac{d^2X}{dt^2} $は慣性系から見た物体の加速度、$ \frac{d^2X’}{dt^2} $は非慣性系から見た物体の加速度、そして$ \frac{d^2X_0(t)}{dt^2} $は非慣性系の原点の加速度です。
慣性系においては、ニュートンの運動方程式$F = m \frac{d^2X}{dt^2}$が成り立つはずです。
この式に、先ほどの関係式を代入してみます。
$$F = m \left( \frac{d^2X’}{dt^2} + \frac{d^2X_0(t)}{dt^2} \right)$$
この式を、非慣性系から見た運動方程式の形に変形してみましょう。つまり、非慣性系から見た加速度$ \frac{d^2X’}{dt^2} $を左辺に持ってきます。
$$m \frac{d^2X’}{dt^2} = F – m \frac{d^2X_0(t)}{dt^2}$$
この式は、非慣性系から見ると、物体の質量に非慣性系での加速度を掛けたものが、物体に働く力から、ある量を引いたものに等しい、という形になっています。
ここで、右辺の第二項である$ – m \frac{d^2X_0(t)}{dt^2} $が、慣性力と呼ばれるものです。
$$F_{\text{慣性}} = – m \frac{d^2X_0(t)}{dt^2}$$
この式を見ると、慣性力は、物体の質量$m$と、非慣性系の原点の加速度$ \frac{d^2X_0(t)}{dt^2} $に比例し、その向きは加速度と逆向きであることがわかります。
例えば、電車が加速すると、私たちは進行方向と逆向きに押されるように感じます。この現象は、この式で説明することができます。
慣性力の例:フリーフォール
慣性力を考える上で、遊園地のアトラクション「フリーフォール」はとても分かりやすい例だと思いました。
フリーフォールが自由落下しているとき、乗っている人は、まるで無重力になったかのように感じます。この現象を慣性系の視点と非慣性系の視点で見てみましょう。
この人から見ると、自由落下している物体には、重力$F = mg$という下向きの外力が働いています。そして、その物体の加速度は重力加速度$g$なので、運動方程式$mg = m \frac{d^2X}{dt^2}$が成り立っています。
この人から見ると、自分や周りの物体は静止しているように見えます。
しかし、実際には重力が働いているはずなのに、なぜでしょうか?
それは、この観測者は自由落下という加速度運動をしている「非慣性系」の中にいるからです。この系で運動を考えると、下向きに働く重力に加えて、上向きに慣性力$F_{\text{慣性}} = -m(-g) = mg$が働いているように見えるのです。
この結果、重力と慣性力がちょうど打ち消し合い、物体には力が働いていないように感じられる、ということになります。これが、あの「無重力」感覚の正体なのだと思います(たぶん)。
この「慣性力」を導入することで、加速している非慣性系の中でも、慣性系と同じように運動方程式が使えるようになるのです。
この考え方は、アインシュタインの一般相対性理論の出発点にもなっています。重力と慣性力が等価である、という「等価原理」の考え方につながっていきます。
まとめ
今回は、慣性系では存在しない「見かけの力」、慣性力についてまとめてみました。座標系を変換するという少し抽象的な話でしたが、遊園地のフリーフォールを例に考えると、感覚的にも理解しやすかったように思います。
ちなみに筆者は不勉強で、はじめ力学で触れたときにはあまり理解ができず、電磁気学と相対論を勉強して座標の変換に関して納得感が高まったような気がします…。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。
古典力学ノート シリーズ一覧
- 古典力学ノート #1:ニュートン力学の基本原理とエネルギーの概念について
- 古典力学ノート #2:運動量と力積、そして運動量保存則について
- 古典力学ノート #3:回転の勢いを表す「角運動量」について
- 古典力学ノート #4:見かけの力「慣性力」について
- 古典力学ノート #5:回転系に現れる「遠心力」と「コリオリ力」
- 古典力学ノート #6:理想の物体「剛体」の運動方程式
- 古典力学ノート #7:回転のしにくさを表す「慣性モーメント」

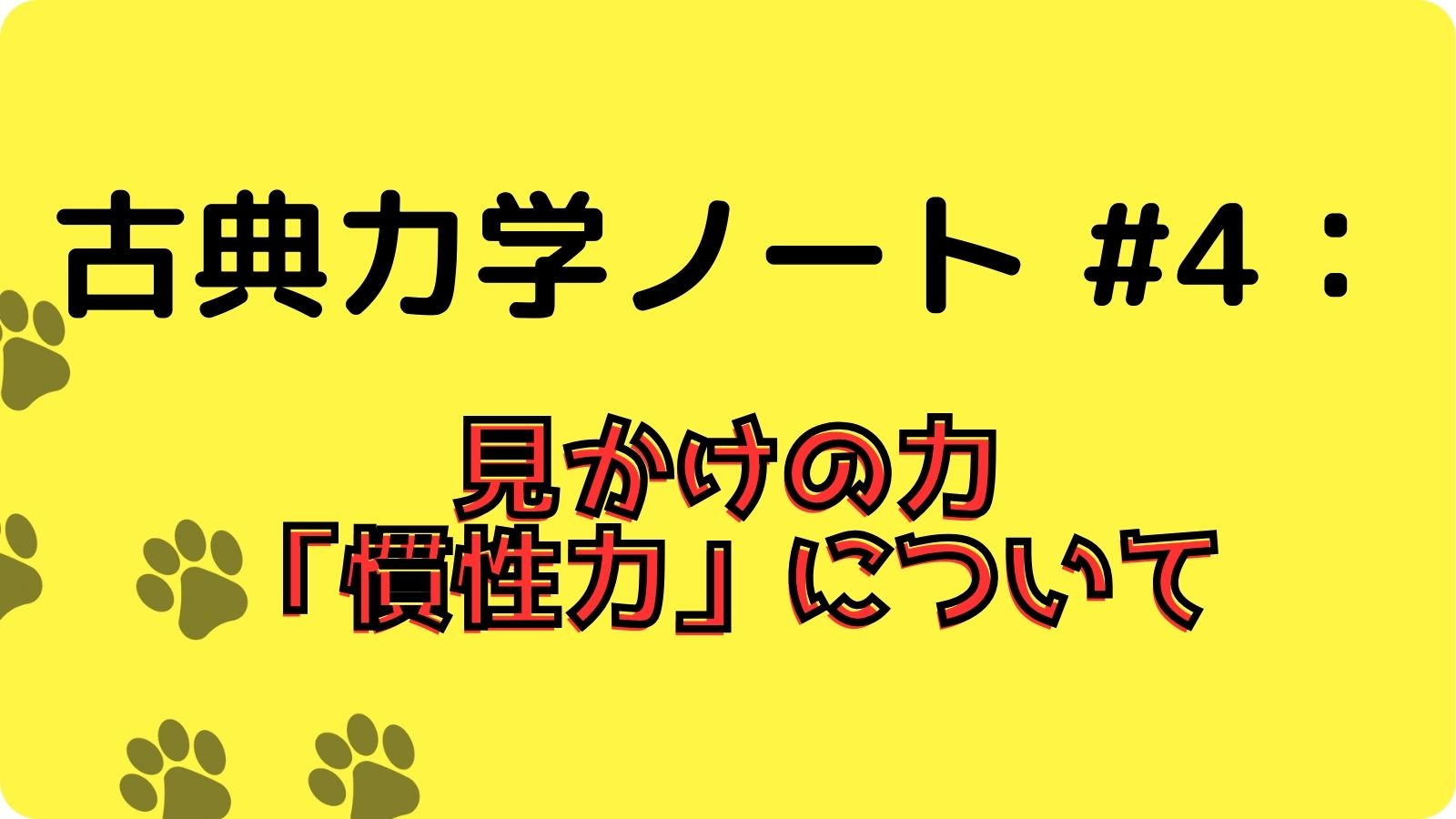


コメントを残す