回転の勢いを表す「角運動量」について
これまでの記事では、運動方程式や運動量について触れてきました。これらは主に、直線的な運動の「勢い」を考えるためのものだったように思います。
今回は、「回転の勢い」を表す、「角運動量」という概念についてまとめてみました。フィギュアスケートの選手が腕をすぼめると回転が速くなる、といった現象も、この角運動量で説明できるようです。
角運動量の定義
角運動量は、記号では$\vec{L}$と書かれることが多いようです。これは、物体の位置と、運動量を掛け合わせた量として定義されます。ただし、単純な掛け算ではなく、「ベクトル積(外積)」という特殊な掛け算を使うのがポイントです。(外積の計算については補足で述べます)
位置ベクトルを$\vec{r}$、運動量を$\vec{p}$とすると、角運動量$\vec{L}$は次のように定義されます。
$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$
ここで、$\vec{p} = m\vec{v}$(質量$m$に速度$\vec{v}$を掛けたもの)でしたね。これを代入すると、もう一つの定義式が得られます。
$$\vec{L} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$
ベクトル積は、二つのベクトルの両方に垂直な方向を向くベクトルを返す演算なので、角運動量$\vec{L}$もまたベクトル量です。その向きは、「右ねじの法則」に従います。つまり、位置ベクトル$\vec{r}$から運動量$\vec{p}$の向きに右ねじを回したときに進む方向が、角運動量$\vec{L}$の向きになります。
角運動量は、その名の通り、物体の回転の度合いを表す量だと考えると分かりやすいかもしれません。
運動方程式からの導出:角運動量とトルクの関係
運動量と同様に、角運動量も運動方程式から導き出されます。
出発点は、前回までと同じ、運動方程式$\vec{F} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$です。
この式の両辺に、位置ベクトル$\vec{r}$をベクトル積として掛け合わせてみます。
$$ \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \left(m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}\right)$$
ここで、左辺の$\vec{r} \times \vec{F}$は、トルク(力のモーメント)と呼ばれる量で、$\vec{N}$と書かれることが多いようです。トルクは、物体を回転させようとする力の影響を表します。
$$\vec{N} = \vec{r} \times \vec{F}$$
次に、右辺について考えてみます。少し複雑な計算になるのですが、ベクトル積の微分に関する法則を使うと、次の関係が導出できます。
$$\frac{d}{dt}(r \times mv) = \frac{dr}{dt} \times mv + r \times \frac{d(mv)}{dt}$$
ここで、$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$であり、$\vec{v}$と$m\vec{v}$は同じ方向を向いているため、$\vec{v} \times m\vec{v}$はゼロになります。
また、$\frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$でしたので、右辺の第2項は$\vec{r} \times \vec{F}$となります。
したがって、
$$\frac{d}{dt}( \vec{r} \times m \vec{v}) = \vec{r} \times \vec{F}$$
という関係が導き出されます。
これを、先ほどの運動方程式に位置ベクトルを掛けた式に当てはめると、次のようになります。
$$ \vec{N} = \frac{d}{dt}( \vec{r} \times m \vec{v})$$
そして、右辺の$\vec{r} \times m\vec{v}$は、まさに角運動量$\vec{L}$の定義そのものですから、
$$ \vec{N} = \frac{d \vec{L}}{dt}$$
という、非常に美しい関係式が導かれます。この式は、「物体に働くトルクは、その物体の角運動量の時間変化に等しい」ということを示しています。
角運動量保存則
さて、この$\vec{N} = \frac{d\vec{L}}{dt}$という関係から、角運動量も「保存量」となる条件を考えることができます。
もし、物体に働く外力によって生じるトルク$\vec{N}$がゼロになる場合、$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$となります。これはつまり、角運動量$\vec{L}$が時間によって変化しない、ということになります。
では、どんな場合にトルクがゼロになるのでしょうか?
これは、外力と位置ベクトルが平行な場合です。
位置ベクトルを$\vec{r}$、外力を$\vec{F}$とすると、トルク$\vec{N} = \vec{r} \times \vec{F}$でした。
ベクトル積の性質上、二つのベクトルが平行(または反平行)である場合、そのベクトル積はゼロになるからです。
このような力を「中心力」と呼びます。中心力とは、力の向きが常に、ある固定された中心点(原点)を向いているような力のことです。
中心力の代表的な例が、万有引力です。
太陽系において、太陽を原点と考えると、地球に働く万有引力は常に太陽の中心を向いています。そのため、地球の位置ベクトルと万有引力は常に平行(正確には反平行)になります。このことから、太陽と地球からなる系では、角運動量は保存されることになります。ケプラーの法則なども、この角運動量保存則から導き出せます。
最後に一点、注意点があります。角運動量は、その値が座標の「原点」の取り方によって変わってしまう、という点です。これは、角運動量の定義に位置ベクトル$\vec{r}$が入っているためです。原点をどこに設定するかによって、$\vec{r}$の値が変わるので、それに伴って$\vec{L}$の値も変わってしまうのです。
まとめ
今回は、回転運動の「勢い」を表す角運動量についてまとめてみました。
前回までの運動量と似ているようで、ベクトル積という新しい演算が出てきて、少し難しかったように感じるかもしれません。しかし、電磁気学を勉強するとベクトル解析をたくさん使うため、もしかすると後ほど改めて触れてみると意外と簡単に理解できるかもしれません。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
[※補足]外積のイメージと計算方法について
力学では、2つのベクトルを掛け合わせる演算として「内積(スカラー積)」の他に、もう一つ重要な「外積(ベクトル積)」があります。これは、回転やトルクといった概念を理解するために不可欠な道具です。
外積の物理的イメージ:面に垂直な方向
外積は、
「2つのベクトル $\vec{A}$ と $\vec{B}$ が張る平面(平行四辺形)に対して、垂直な方向を示す新しいベクトル」
として誕生した概念です。この新しいベクトルは、元の2つのベクトルが張る平行四辺形の面積に比例する大きさも持っています。
具体的には、$\vec{A}$ から $\vec{B}$ へと右ねじを回す方向(または右手の法則)に垂直な方向を指します。
この新しいベクトル $\vec{C}$ の大きさは、$|\vec{C}| = |\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta$ で表され、これは2つのベクトルが張る平行四辺形の面積に他なりません($\theta$ は $\vec{A}$ と $\vec{B}$ のなす角)。
外積の計算方法
成分表示されたベクトル $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ と $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ の外積は、行列の余因子展開(あるいはサラスの規則)に似た形式で計算できます。これは、基底ベクトル $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ を形式的に使った3行3列の行列の行列式として表現されます。
この行列式を展開すると、以下のようになります。
各成分ごとに見ると、確かに引き算の形で現れていますね。
外積が使われる例
- トルク(力のモーメント): $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$ (回転させる効果)
- 角運動量: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ (回転運動の量)
- ローレンツ力: $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ (電荷が磁場中で受ける力)
これらの物理量はいずれもベクトル量であり、その方向が物理現象を記述する上で重要になります。
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。
古典力学ノート シリーズ一覧
- 古典力学ノート #1:ニュートン力学の基本原理とエネルギーの概念について
- 古典力学ノート #2:運動量と力積、そして運動量保存則について
- 古典力学ノート #3:回転の勢いを表す「角運動量」について
- 古典力学ノート #4:見かけの力「慣性力」について
- 古典力学ノート #5:回転系に現れる「遠心力」と「コリオリ力」
- 古典力学ノート #6:理想の物体「剛体」の運動方程式
- 古典力学ノート #7:回転のしにくさを表す「慣性モーメント」

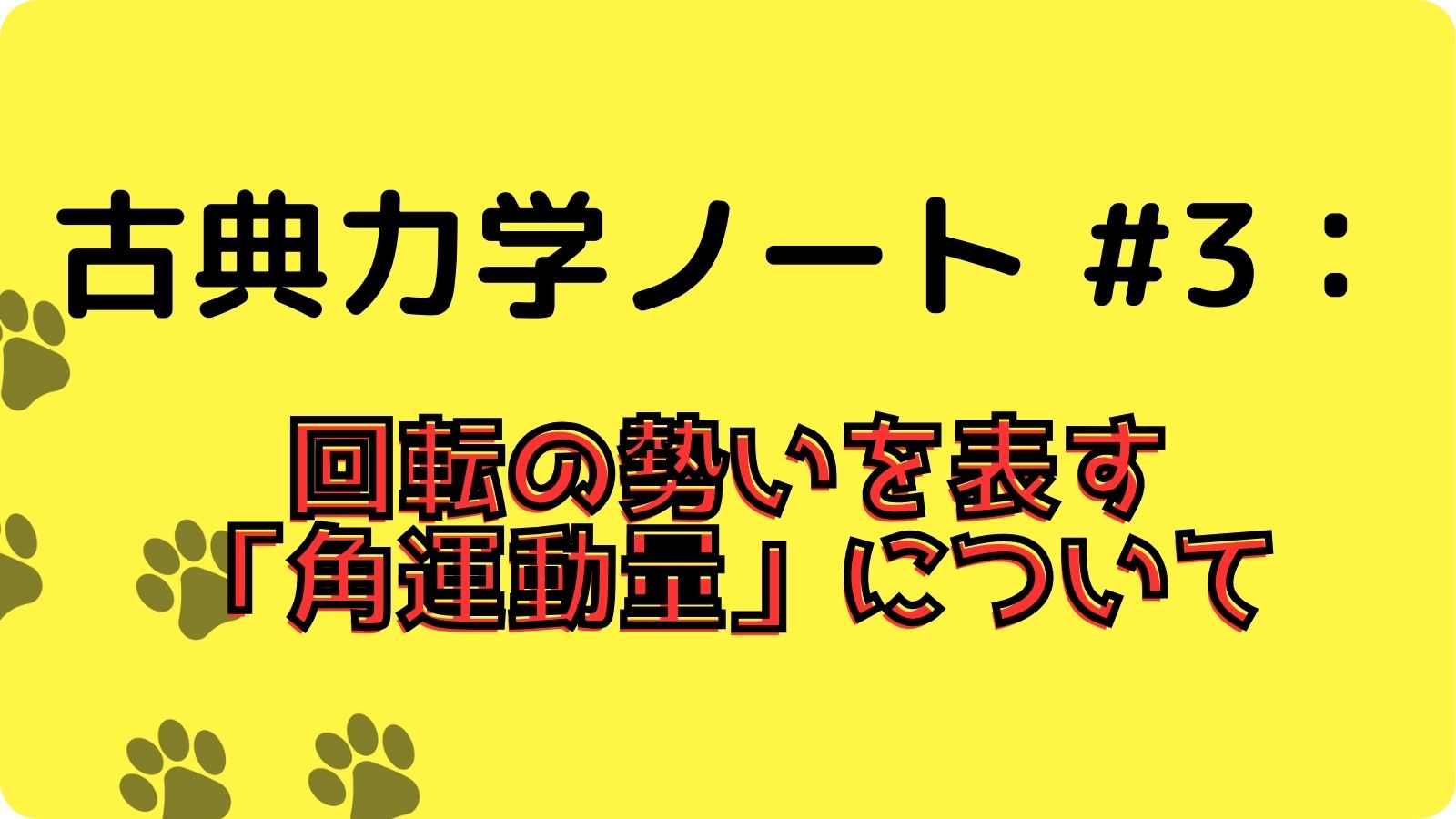


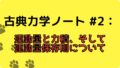
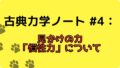
コメントを残す