運動量と力積、そして運動量保存則について
こんにちは。前回の記事では、ニュートン力学の三つの法則と、そこから導かれるエネルギーについてまとめてみました。
今回は、前回に引き続き、運動方程式から導かれるもう一つの重要な概念、「運動量」についてまとめてみました。エネルギーとは少し違った視点で物体の運動を捉えることができます。
ちなみに、ベクトルは太字表記するのが理学書では定番ですが、記事内では見えにくいので矢印をつけた表記をしています。
運動量の定義
まず、運動量とは何でしょうか。とてもシンプルに言うと、物体の質量と速度を掛け合わせたものとして定義されます。
高校物理などでは、単に$m\vec{v}$と書かれることが多いかもしれません。
大学に入って、位置や速度をベクトルで考えるようになると、運動量もまたベクトル量であることが強調されます。つまり、運動量は、大きさと向きを持つ物理量ということになります。
記号としては、$p$と書かれることが多いようです。質量を$m$、速度を$\vec{v}$とすると、運動量の定義は次のようになります。
$\vec{p} = m\vec{v}$
この定義は、直感的に物体の「動きの勢い」のようなものを表しているように思います。例えば、同じ速度で動いているとしても、重い物体の方が止まりにくく、より大きな勢いを持っているように感じますよね。
この「勢い」を数学的に表現したのが、運動量なのかな、と個人的には解釈しています。
運動方程式からの導出:運動量と力積の関係
前回も登場した運動方程式は、古典力学のあらゆる議論の中心にあるように思います。運動量も、この方程式から自然に導かれます。
運動方程式は、力$\vec{F}$と加速度$\vec{a}$の関係を$\vec{F }= m\vec{a}$と表しました。
ここで、加速度$\vec{a}$は速度$\vec{v}$の時間微分、つまり$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$でしたね。これを運動方程式に代入すると、次のようになります。
$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$
ここで、質量$m$が時間的に変化しないと仮定します。そうすると、質量$m$を時間微分の記号$d/dt$の中に入れることができるでしょう。これは、微分演算子の線形性という性質からできます。
$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$
この式の右辺の$m\vec{v}$こそが、まさに先ほど定義した運動量$\vec{p}$に他なりません。
$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$
この式は、「物体に働く力は、その物体の運動量の時間変化に等しい」ということを示しているように思えます。つまり、力を加えれば運動量が変化し、力を加えない限り運動量は変化しない、というニュートンの第一法則とも見事に整合しているように見えます。
ニュートンがプリンキピアで運動方程式を導入した際には、運動量の時間微分で記述されていたという話を見たことがあります。
次に、この式の両辺を時間で積分してみましょう。ある時刻$t_1$から$t_2$までの間で積分すると、
$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \,dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt$
左辺の$\int \vec{F} \,dt$は、力積と呼ばれる量です。力$\vec{F}$を、ある時間$dt$の間加え続けた効果を全て足し合わせたもの、と考えると分かりやすいかもしれません。
一方、右辺は微分の逆演算である積分なので、端点の値の差になります。
$\int_{t_1}^{t_2} \frac{dp}{dt} dt = [p]_{t_1}^{t_2} = p(t_2) – p(t_1)$
したがって、次の関係式が導き出されます。
$\int_{t_1}^{t_2} F \,dt = p(t_2) – p(t_1)$
この式は、「物体に与えられた力積は、その物体の運動量の変化に等しい」ということを示しています。この関係は運動量と力積の関係といいます。
運動量保存則
さて、力積の概念がわかると、次に「運動量保存則」を考えることができます。先ほどの式をもう一度見てみましょう。
$\int_{t_1}^{t_2} F \,dt = p(t_2) – p(t_1)$
もし、この式の左辺、つまり力積がゼロになる場合はどうなるでしょうか?
$0 = p(t_2) – p(t_1)$
これを変形すると、
$p(t_1) = p(t_2)$
となります。これは、時刻$t_1$の運動量と時刻$t_2$の運動量が等しい、つまり運動量が時間によって変化しない、ということを意味してます。これが「運動量保存則」です。
では、どんな場合に力積がゼロとみなせるのでしょうか?
考えられる状況はいくつかあります。
- ① 物体に働く外力がゼロの場合:これは単純に$F=0$なので、力積もゼロになります。
- ② 力が非常に短い時間しか働かない場合:例えば、ビリヤードの球が衝突する瞬間などです。衝突の瞬間は非常に大きな力が働きますが、その時間が極めて短いため、力と時間の積である力積がほとんどゼロとみなせる、という考え方もあります。
- ③ 複数の物体からなる系全体を考える場合:この場合、系内の物体同士が及ぼし合う力は「作用・反作用の法則」により互いに打ち消し合います。したがって、系全体に働く外力がゼロであれば、系の全運動量が保存されることになります。
特に、③の複数の物体からなる系を考える場合が、運動量保存則の最も重要な応用例の一つではないかと思います。
例えば、ロケットの噴射や、物体の分裂・合体といった現象は、運動量保存則を使うととてもきれいに説明できるそうです。
まとめ
今回は、運動方程式から導かれるもう一つの重要な量、運動量についてまとめてみました。運動量や力積といった概念は、衝突や分裂のような、一瞬で物体の運動が大きく変わるような現象を解析する際に、とても役立ちます。
物理学には、今回のような「保存則」と呼ばれる法則がいくつかあります。前回お話した「力学的エネルギー保存則」もその一つでしたね。これらの保存則は、運動の詳細な過程がわからなくても、物体の始点と終点の状態を結びつけてくれるツールのように感じています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
[補足]Q&A:ベクトルの定積分はスカラー?
「力を時間で積分すると、最終的な結果はスカラーになるのか?」
結論から言うと、答えは「ベクトル量」です。今回は、この物理的な意味を併せて掘り下げて考えてみましょう。
スカラーとベクトルの定積分
数学では、$\int_a^b f'(x) dx = f(b) – f(a)$ という微分積分学の基本定理を学びます。ここで、関数$f(x)$がスカラー量であれば、最終的な結果もスカラーになります。しかし、物理学では積分する対象がスカラーかベクトルかを区別する必要があります。
力 $\vec{F}(t)$ は、時刻$t$に依存するベクトル量です。これは、大きさと共に「向き」を持つ量です。このベクトル量を時間で定積分する場合、数学的には各成分を個別に積分します。
$ = \left(\int_{t_1}^{t_2} F_x(t) dt\right)\vec{i} + \left(\int_{t_1}^{t_2} F_y(t) dt\right)\vec{j} + \left(\int_{t_1}^{t_2} F_z(t) dt\right)\vec{k} $
ご覧の通り、定積分の結果も各成分を持つベクトル量になります。
力積と運動量の関係
物理的な意味を考えると、この疑問はさらに明確になります。ニュートンの運動方程式 $\vec{F}(t) = m\frac{d\vec{v}}{dt}$ を時間で定積分してみましょう。
$ = [m\vec{v}(t)]_{t_1}^{t_2} $
$ = m\vec{v}(t_2) – m\vec{v}(t_1) $
ここで、$m\vec{v}(t)$ は運動量 $\vec{p}(t)$です。運動量も力と同じくベクトル量です。したがって、この式は以下のように書けます。
この結果は、力積が運動量の変化量($\Delta \vec{p}$)に等しいことを示しています。運動量の変化は、向きと大きさを持つベクトルから、同じく向きと大きさを持つベクトルを引く操作です。そのため、最終的な結果もやはりベクトル量になります。
<補足まとめ>:
力(ベクトル)を時間で定積分した結果は「力積」であり、これは運動量の変化(ベクトル)に等しい。
定積分の結果がスカラーになるのは、積分する対象がスカラー量の場合のみです。ベクトル量を積分した結果は、基本的にベクトル量になります。
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。
古典力学ノート シリーズ一覧
- 古典力学ノート #1:ニュートン力学の基本原理とエネルギーの概念について
- 古典力学ノート #2:運動量と力積、そして運動量保存則について
- 古典力学ノート #3:回転の勢いを表す「角運動量」について
- 古典力学ノート #4:見かけの力「慣性力」について
- 古典力学ノート #5:回転系に現れる「遠心力」と「コリオリ力」
- 古典力学ノート #6:理想の物体「剛体」の運動方程式
- 古典力学ノート #7:回転のしにくさを表す「慣性モーメント」

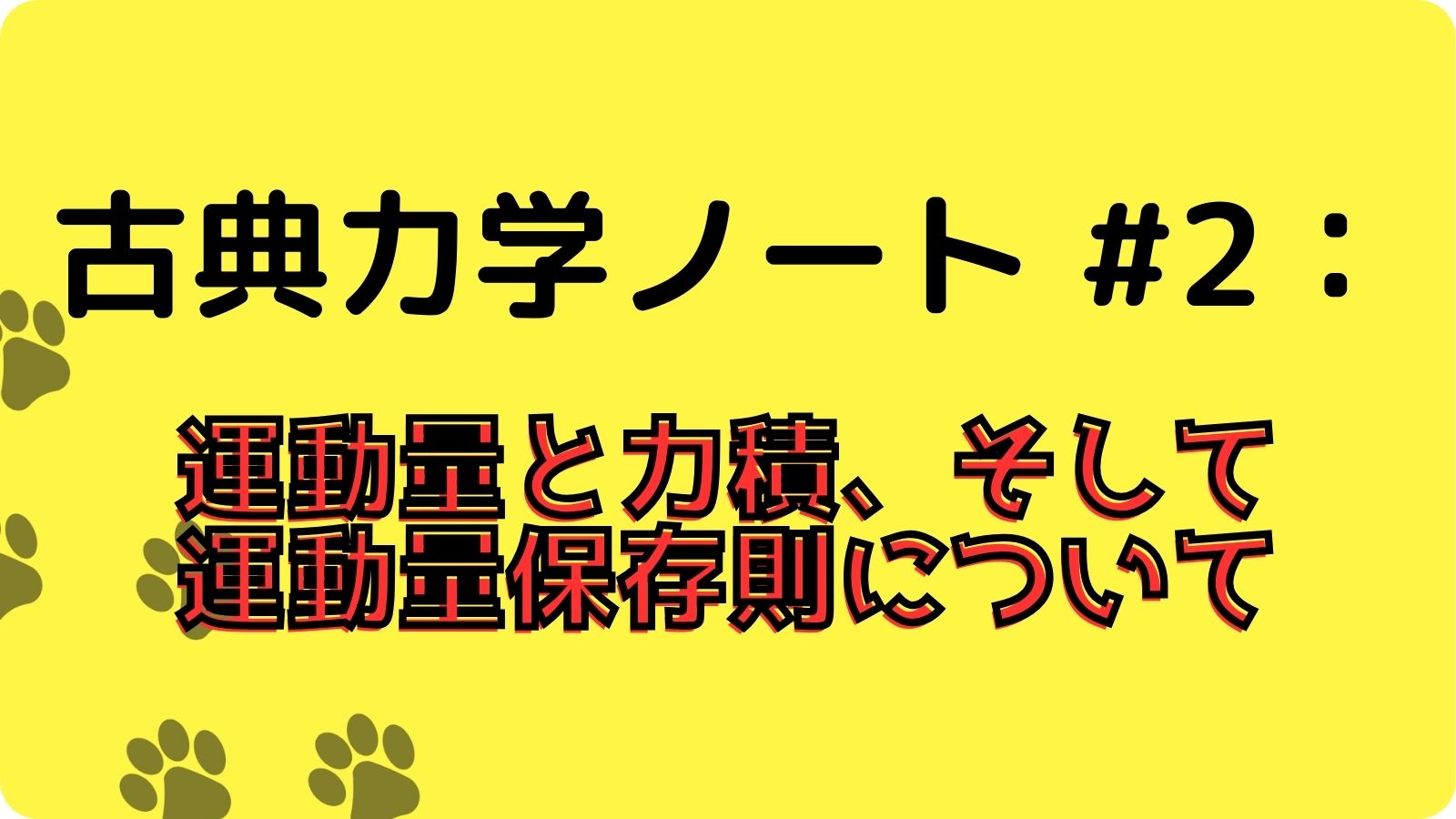


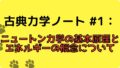
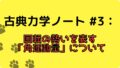
コメントを残す