【意外な共通点】薩長同盟はデリバティブ取引だった?勉強会の備忘録
この前の勉強会でデリバティブ取引と言う用語を知りました。
そこで、たまには趣の違う話も考えてみようと思いました。
「デリバティブ取引」と聞いて、あなたはどんなイメージを持つでしょうか?
きっと多くの人が「なんだか難しそう」「金融の専門用語だろう」と感じるはずです。私もその一人でした。しかし、先日、ある勉強会で聞いた「薩長同盟もデリバティブ取引の一種である」という話を聞いて、何となくですが概観が掴めたような気がしました。
今回は、一見まったく関係のない「金融工学」と「歴史」を繋げて考えることで、デリバティブ取引について紐解いてみたいと思います。
デリバティブ取引とは何か?
デリバティブ取引を一言で言うなら、「未来の不確実なリスクを、特定の形で交換する取引」です。例えば、未来の価格変動や金利変動といったリスクを、お互いのニーズに合わせて交換します。
ただリスクを交換するだけでは意味がありません。お互いの得意なことや苦手なことを交換することで、それぞれが抱えるリスクを回避し、より安定した状況を作り出すことができます。これはまるで、不測の事態に備える保険のような考え方とも言えるのではないでしょうか?
薩長同盟に隠された「デリバティブ取引」の本質
それでは、このデリバティブ取引の考え方を、日本の歴史に登場する「薩長同盟」に当てはめてみましょう。
当時の薩摩藩と長州藩が抱えていたリスクとリソース
-
薩摩藩:幕府に信頼されており、軍艦や銃を容易に購入できるという強みがありました。しかし、長年の米不足に悩まされ、経済的に不安定な状況でした。
-
長州藩:経済力はありましたが、幕府と対立関係にあったため、武器商人から武器を売ってもらえず、軍事力が弱いというリスクを抱えていました。
このように、薩摩藩は「コメ不足」というリスクを、長州藩は「武器不足」というリスクを抱えていたのです。
坂本龍馬の仲介が「スワップ取引」だった?
ここで登場するのが、坂本龍馬です。龍馬は、この両者のニーズとリスクを見抜き、次のような取引を提案しました。
「薩摩藩の信頼性を利用して、薩摩名義で武器を購入する。そして、その見返りとして、長州藩が持つ経済力(米や資金)を薩摩藩に提供する。」
この取引は、お互いの得意なこと(リソース)を交換することで、苦手なこと(リスク)を補い合うという点で、デリバティブ取引、特に個別のニーズに合わせて条件を設計する「スワップ取引」そのものです。
まとめ:専門用語の本質を捉える面白さ
「デリバティブ」と「薩長同盟」という、一見無関係な分野を結びつけるこの思考法は、物事の本質を理解する上で非常に役立ちます。
専門用語は、ただ暗記するのではなく、身近な例や異なる分野に当てはめて考えてみると、驚くほど簡単に、そして深く理解できることがあります。これからも、日々の学びをこうしたユニークな視点で捉え直し、自分だけの「備忘録」としてストックしていくことで、色々と見識を深めていけたらと思っています。
参考資料
今回のお話は、歴史好きの勉強会メンバーから聞いた話をブログにしています。そのため出典がよくわからない情報でしたが、勉強会のあと気になってネットで調べた際に参考にしたサイト様です。

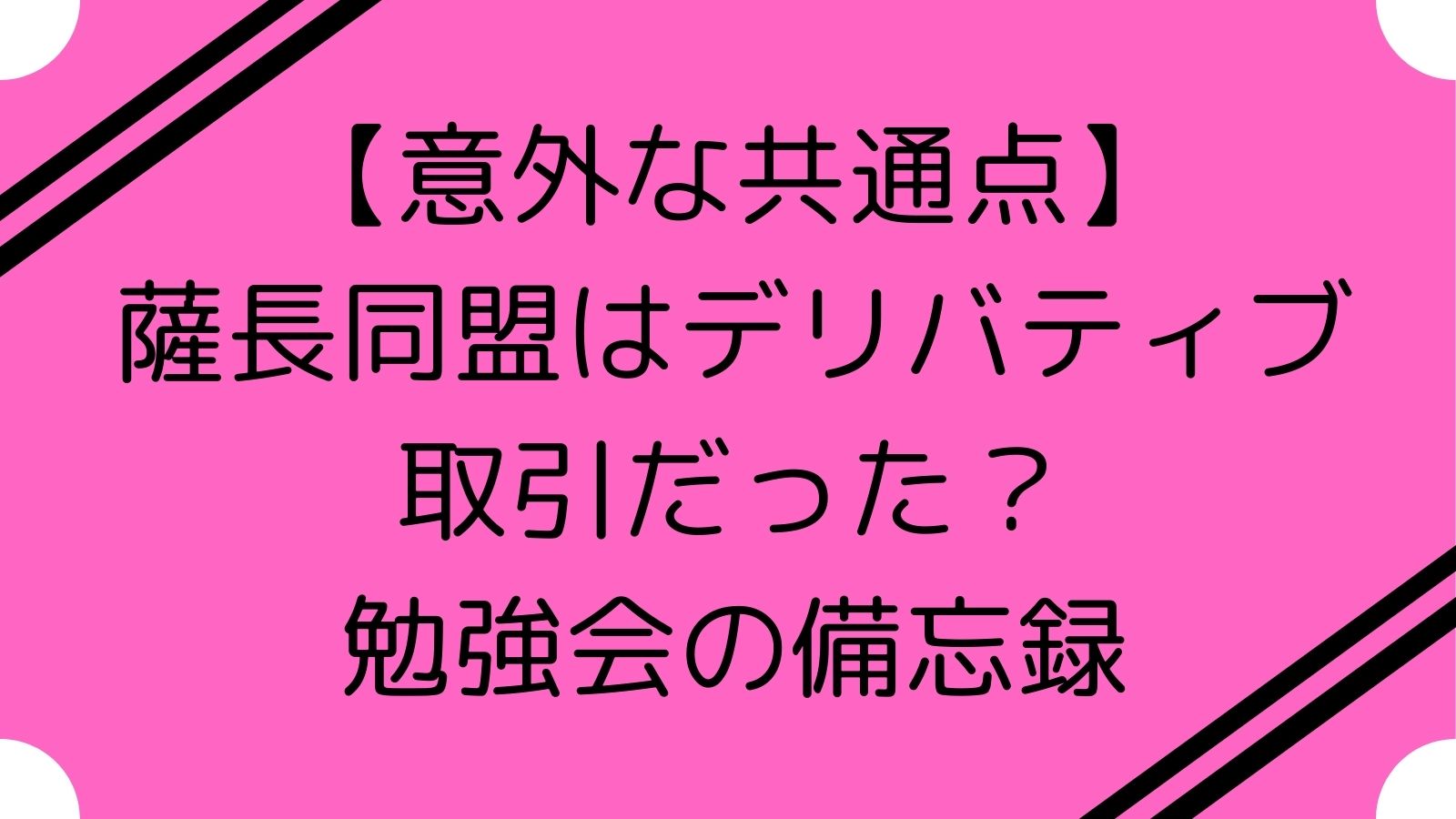



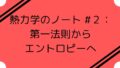
コメント