『勉強会カテゴリー/タグ』についての背景や取扱については”コチラ”をご覧ください.
中学数学の学び直し!特別編:プログラミングに役立つ「写像」の考え方
1. 写像とは?
「写像」とは、ある集合の要素を、別の集合の要素に対応させる規則のことです。
なんだか難しく聞こえますが、実は非常に身近な概念です。例えば、自動販売機を考えてみましょう。
【自動販売機と写像】
- 定義域(入力):あなたが押すボタンの集合(例: {ボタンA, ボタンB, ボタンC})
- 値域(出力): 出てくる飲み物の集合(例: {お茶, コーヒー, ジュース})
- 写像(規則): 「ボタンAを押すとお茶が出てくる」という対応関係
この「ボタンを押す」という行為が「お茶が出てくる」という結果に対応する、この対応関係こそが「写像」です。この考え方は、プログラミングにおける関数と全く同じです。関数は、入力(引数)を受け取って、特定の規則に従い出力(戻り値)を返します。この入力から出力への対応関係が「写像」なのです。
2. プログラミングと写像
プログラミングのあらゆる場面で、この「写像」の考え方が使われています。たとえば、文字列を大文字に変換する関数を考えてみましょう。
この処理をPythonで書くと次の様に書けます。
“`python
# Python
text = “hello world”
# .upper()という関数は、文字列を大文字の文字列に「写像」する
upper_text = text.upper()
print(upper_text) # “HELLO WORLD”
“`
# Python
text = “hello world”
# .upper()という関数は、文字列を大文字の文字列に「写像」する
upper_text = text.upper()
print(upper_text) # “HELLO WORLD”
“`
この例では、元の文字列という集合から、大文字の文字列という集合への「写像」が行われています。このようなデータの変換や加工は、プログラミングでは頻繁に行われます。
3. まとめと今後の学習
今回は、関数をより深く理解するための「写像」の考え方を解説しました。
「写像」は、あるデータ集合から別のデータ集合への対応関係です。この概念を意識することで、プログラムがどのようなデータをどのように加工しているかを、より論理的に捉えられるようになります。
この考え方は、今後のデータ構造やアルゴリズムの学習にも役立ちます。ぜひ、日々のコーディングで「この関数は、何を何に写像しているんだろう?」と考えながら取り組んでみてください。
連載の続きはこちら!

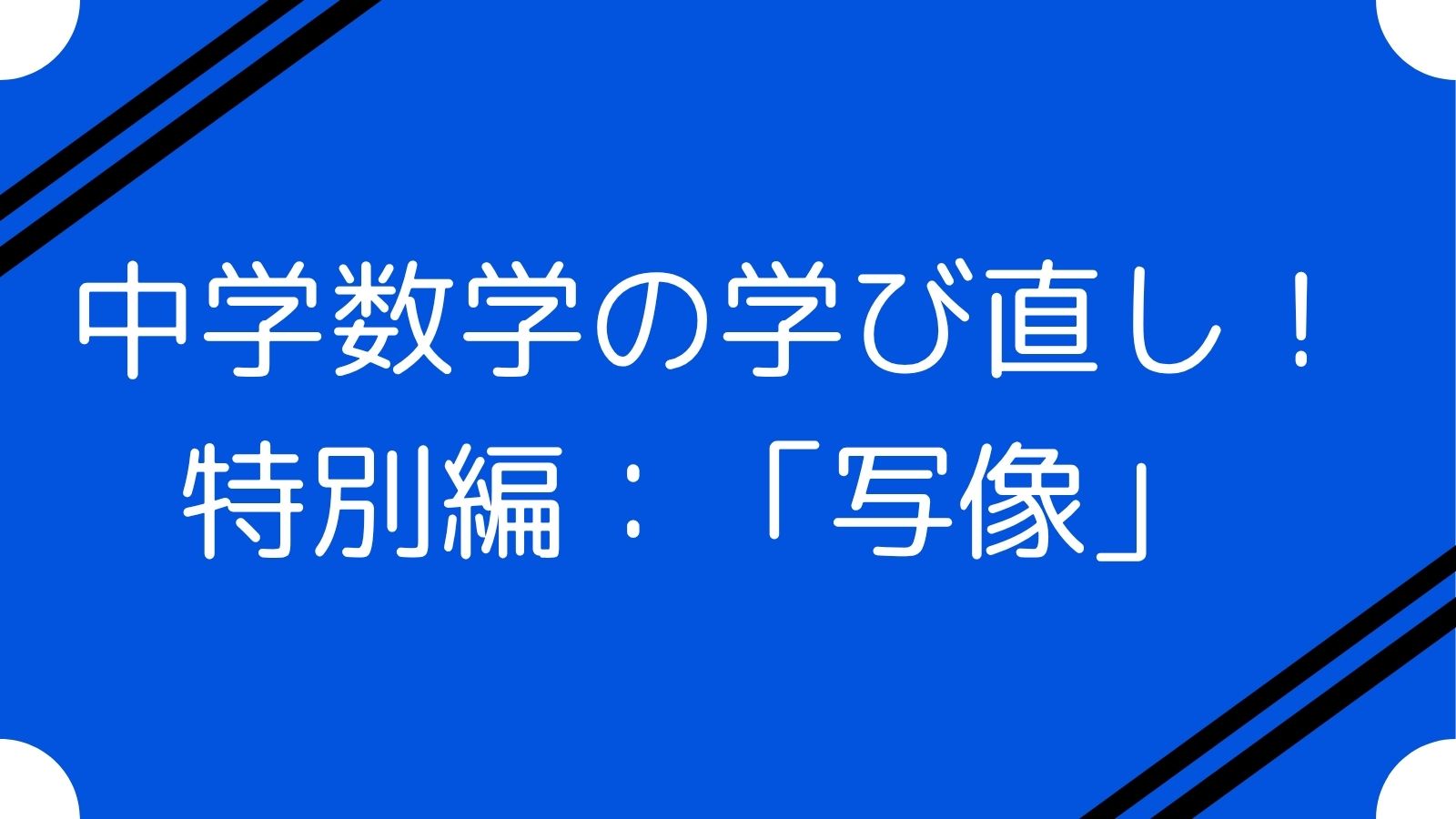



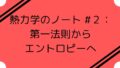
コメント