『勉強会カテゴリー/タグ』についての背景や取扱については”コチラ”をご覧ください.
中学数学の学び直し!第1回:変数と文字式の考え方
1. 変数とは?
中学数学では、未知の数や変わる可能性のある数を$x$や$y$といった文字で表しましたね。これが「変数」です。
プログラミングでも全く同じです。$x$や$y$のような名前(変数名)をつけた「データを格納する箱」だと考えればOKです。
たとえば、$x = 10$というコードは、「$x$という名前の箱に10という数字を入れる」という意味になります。箱の中身は、いつでも新しい値に上書きできます。
例えば、この処理をPythonで書くとこの様に書けます。
“`
# Python
x = 10
x = x + 5 # xは15になる
“`
# Python
x = 10
x = x + 5 # xは15になる
“`
このように、変数はデータに名前をつけ、一時的に保存するために使われます。
2. 文字式とは?
中学数学では、$2x + 3$や$x + y$のような文字を使った式を学びました。これが「文字式」です。
文字式は、プログラミングでは「式」として扱われます。変数がどのような計算に使われるかを示す、いわば「レシピ」や「指示書」のようなものです。$x$にどんな値が入っても、決まった計算をすることができます。
例えば、この処理をPythonで書くとこの様に書けます。
“`
# Python
x = 10
y = 5
result = 2 * x + y # resultには25が入る
“`
# Python
x = 10
y = 5
result = 2 * x + y # resultには25が入る
“`
文字式を理解することで、どんな値が入っても正しく動作する汎用的なプログラムを作ることができるようになります。
3. まとめと次回予告
今回は、プログラミングの基礎である「変数」と「文字式」の考え方を中学数学の視点から解説しました。
「変数」はデータを一時的に保存する箱、「文字式」はそのデータを使って行う計算のレシピです。これらを理解することで、柔軟で汎用性の高いプログラムを書くための土台ができます。
次回は、プログラミングでも重要な概念である「集合」と「演算」について解説します。
連載の続きはこちら!

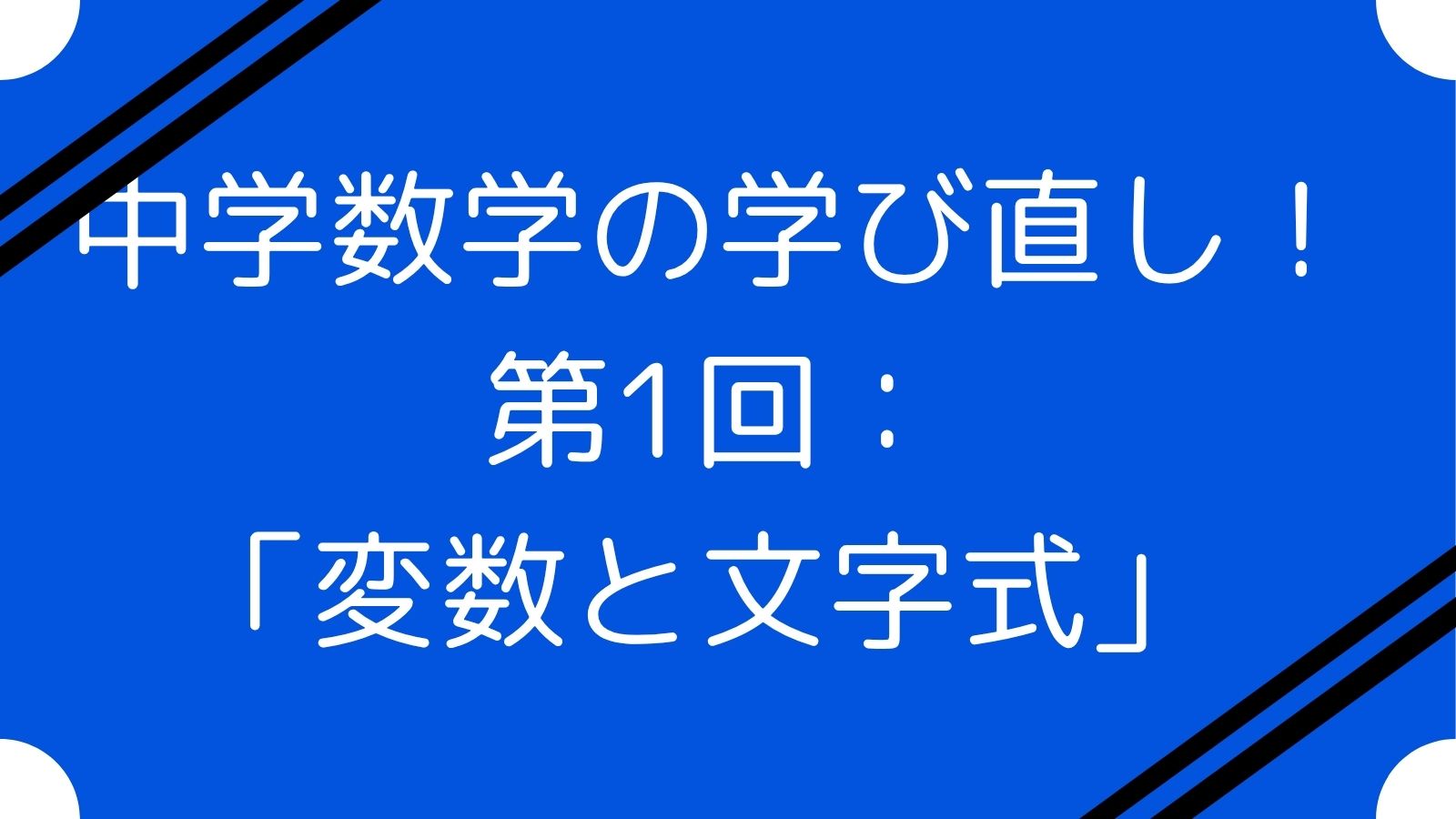



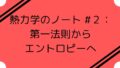
コメント