1/5
運動方程式から保存則へ:物理学の全体像を概観する
今回は、勉強会で学んだ物理学の全体像について、備忘録としてまとめていきます。物理学が何を目的とし、どのような考え方で世界を記述しようとしているのか、その大きな流れを一緒に見ていきましょう。物理学がしたいこと:「予言」
物理学、特に力学が目指していることは、ある状況(初期条件)から、最終的にどうなるかを予測することです。これを「予言」と表現すると、とても分かりやすいですね。具体的な目標は、ある瞬間の物体の位置や速度を求めることです。 位置や速度を求めるためには、どうすればよいのでしょうか? その鍵となるのが、加速度です。加速度は単位時間あたりの速度の変化、速度は単位時間あたりの位置の変化なので、加速度が分かれば速度が分かり、最終的に位置も求めることができます。物体を落としたときに重力加速度に従う「等加速度運動」から勉強を始めることが多いのは、この加速度が一定だからなのですね。加速度を求めるツール:運動方程式
では、その重要な加速度をどうやって求めるのでしょうか?ここで登場するのが、物理学で最も有名な公式の一つ、運動方程式です。質量を持った物体に力を加えると、加速度が生じることが知られています。加速度は、力に比例し、質量に反比例します。この関係を式で表すと、ニュートンの運動方程式$\vec{F} = m\vec{a}$となります。この式を加速度について変形すると、$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$となり、加速度がどう決まるかが明確に分かります。 ちなみに、この運動方程式の元々の形は、運動量$\vec{p}$の時間微分として記述されることも多いのです。$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$という形ですね。運動量による記述の方が、現代物理学ではより一般的だと思います。(ちなみに現代物理学の基礎となる解析力学は運動量による記述が採用されています。)便利な性質:運動量と保存則
ここで、運動量という概念について深掘りしていきましょう。運動量は、質量に速度を掛けたものです($\vec{p} = m\vec{v}$)。この運動量には、保存して一定になるという非常に便利な性質があります。例えば、二つの物体が衝突するような状況を考えるときに、この運動量保存則が非常に有用です。これは、外から力が働かない系(内力しか働かない系)においては、運動量の総和が変化しないことを意味します。保存則と「対称性」
この保存則の背景には、実は「対称性」という非常に美しい概念が隠されています。保存則は、ネーターの定理というものから導かれます。この定理は、あえて雑に言えば「物理法則がある種の対称性を持つとき、必ず何らかの保存則が成り立つ」というものです。- 運動量保存則:これは、並進対称性(空間のどの位置にいても物理法則が変わらない)に対応しています。
- エネルギー保存則:これは、時間並進対称性(時間の原点をどこに設定しても物理法則が変わらない)に対応しています。宇宙の始まりのような、時間そのものが定義されるような特異点では、この対称性が破れるため、エネルギーは保存していないと考えられているそうです。
- 角運動量保存則:これは、空間回転対称性(どの方向から見ても物理法則が変わらない)に対応しています。例えば、ケプラーの第二法則(惑星と太陽を結ぶ線分が、単位時間あたりに描く面積が一定である)は、太陽と惑星の間に働く力が角度に依存しないため、この角運動量保存則が成り立つことの表れです。
保存則を統合する概念:「作用」
これらの保存則をより一般的に表現する概念として、作用Sというものがあります。これは、ラグランジアンLを時間で積分した量として定義されます。ラグランジアンは、運動エネルギーTから位置エネルギーU(ポテンシャルエネルギー)を引いたものです。このラグランジアンが不変である(対称性を持つ)ならば、必ず保存則が導かれるという関係があります。$S = \int_{t_1}^{t_2} L \,dt$
$L=TーU$
この「作用」の概念を使うと何ができるのでしょうか?それは、最小作用の原理というものが、自然界の基本的な原理となっているからです。この原理は、「自然界の物理現象は、作用が最小になるような経路を通る」というものです。この原理から導かれるオイラー・ラグランジュ方程式(E-L.eq)は、ニュートンの運動方程式と同じ情報を含んでおり、より一般的な形で物理現象を記述できます。 この考え方は非常に強力で、力学だけでなく、電磁気学や相対性理論にも応用されます。アインシュタインの一般相対性理論でも、アインシュタイン=ヒルベルト作用というものを最小にする条件を考えると、アインシュタイン方程式が導出され、時空の歪みや曲がりを記述できるといいます。 今回は、物理の基本的な考え方と、その背景にある「対称性」という深い概念についてまとめました。次回は、相対性理論と、空間の次元についての話に進んでいきたいと思います。全記事一覧
- 物理の全体像:運動方程式から保存則へ (今ココ)
- 物理の全体像:相対性理論と時空の歪み
- 物理の全体像:次元の考察と重力のモデル化
- 物理の全体像:アインシュタイン方程式とブラックホール
- 物理の全体像:量子力学と未来の物理学

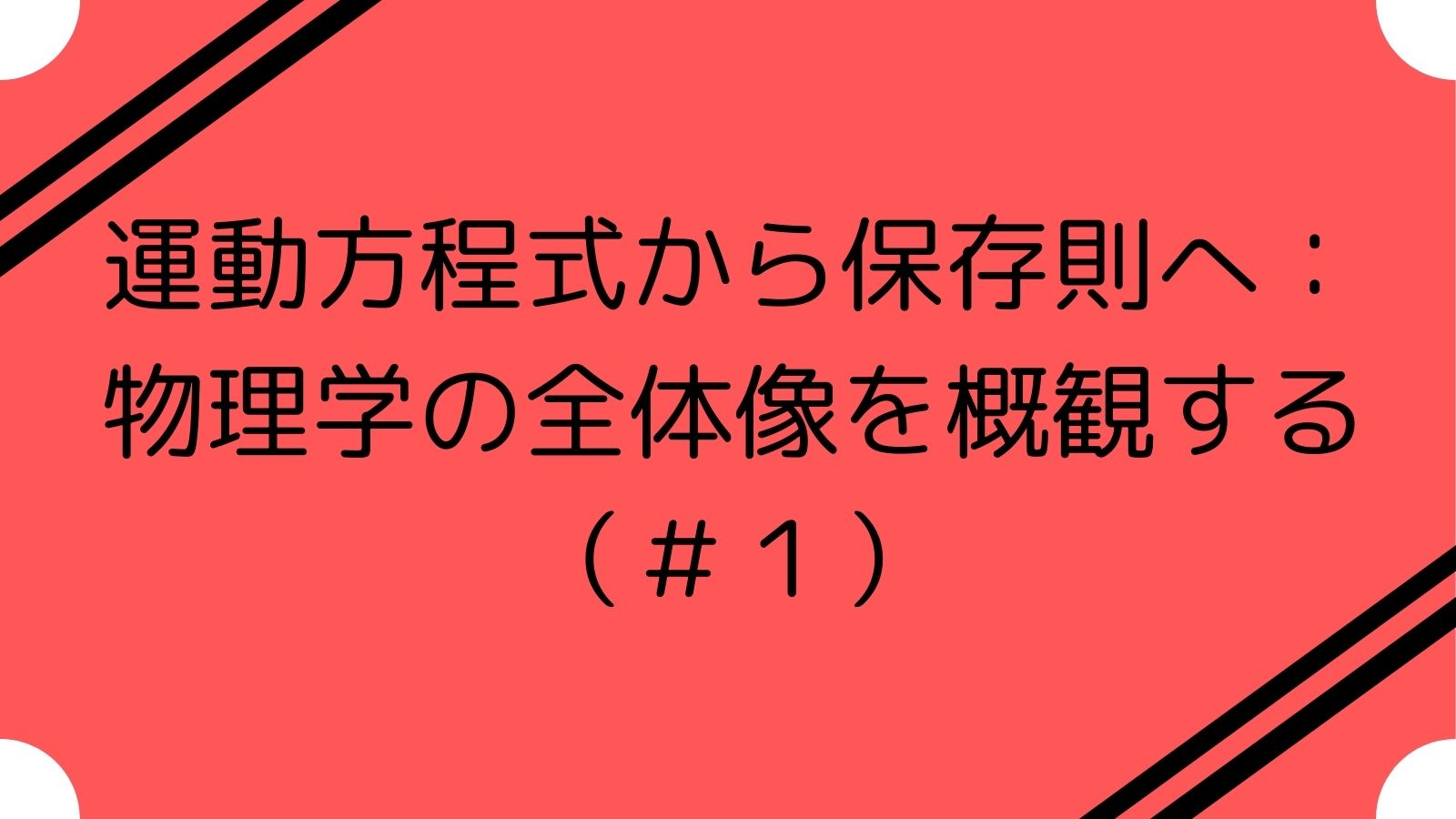


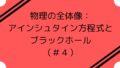
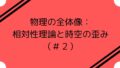
コメント