調和振動子系と井戸型ポテンシャルの量子論的計算
前回の記事では、統計力学の基本的な考え方である「等確率の原理」や「ボルツマンの原理」について書きました。
今回は、これらの原理をより具体的なモデルに適用して、物理量を実際に計算する手順を追ってみたいと思います。
調和振動子系での物理量計算
今回扱うのは、原子がバネでつながったようなモデル、「調和振動子系」です。これは、固体を構成する原子の振動をモデル化する際によく用いられます。
量子力学的な調和振動子のエネルギー
古典的な調和振動子では、エネルギーは連続的に変化しますが、量子力学の世界ではそうではありません。量子力学的な調和振動子のエネルギー準位は、次の式で表されるように、等差数列的に決まります。
$$E = (n + \frac{1}{2})\hbar \omega$$
ここで、$n$は非負の整数($0, 1, 2, …$)、$\hbar$はディラック定数、$\omega$は角振動数です。エネルギーの最小値である$n=0$のときのエネルギー$\frac{1}{2}\hbar\omega$は、「零点エネルギー」と呼ばれますが、計算を簡単にするために今回は無視します。
統計力学の計算では、この量子力学的なエネルギー準位を使って、$N$個の調和振動子系の全エネルギー$E$を考え、それを実現する状態数$W$を数えていきます。この状態数の計算は、「$m$個のリンゴを$N$人に分ける」という組み合わせの問題と等価だと考えることができます。
状態数$W$を計算した後、前回の記事でも登場したボルツマンの原理$S = k_B \ln W$を使ってエントロピー$S$を導出します。この際も、スターリングの公式を用いて近似計算が行われます。
比熱の導出
エントロピー$S$の式が得られれば、熱力学的な物理量を導出できます。まず、$S$を$E$で微分して、温度$T$と$E$の関係式$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$を求めます。
次に、エネルギー$E$を温度$T$で微分することで、定積比熱$C_V$が計算できます。
$$C_V = \frac{\partial E}{\partial T}$$
この比熱の振る舞いを考察すると、低温では比熱が指数関数的にゼロに近づき、高温では$C_V = Nk_B$という一定値に漸近することが示されます。これは、「デュロン=プティの法則」として知られる古典的な法則と一致するようです。
量子力学の基礎:井戸型ポテンシャル
今後の統計力学の議論で、「理想気体」を扱う際に、量子力学的な粒子の振る舞いを理解することが不可欠となります。そこで、その準備として、量子力学の基礎を少しだけおさらいしてみましょう。
古典力学との違い
古典力学では、粒子の位置や運動量は厳密に決まりますが、量子力学ではそうではありません。量子力学では、粒子の状態は確率的にしか決まらないとされています。
波動関数とシュレーディンガー方程式
この確率的な粒子の振る舞いを記述するために、「波動関数$\psi$」が使われます。この波動関数の絶対値の2乗$|\psi|^2$は、その粒子を見つける確率密度に比例します。
この波動関数を決定するのが、量子力学の根幹をなす「シュレーディンガー方程式」です。この方程式を解くことで、波動関数と同時に、その粒子が取りうる「エネルギー固有値$\epsilon$」が決まります。
具体的な計算例
最も簡単な例として、粒子が箱の中に閉じ込められている状況をモデル化した「1次元の井戸型ポテンシャル」を考え、シュレーディンガー方程式を解くと、エネルギー固有値は離散的な値(飛び飛びの値)を持つことが分かります。
さらに、より現実的な3次元の粒子を考える場合も、エネルギーが$E$以下の状態の数$\Omega(E)$は、幾何学的な問題として計算できます。
この量子力学的な「エネルギーの離散性」という概念が、今後の統計力学の議論、特に理想気体の振る舞いを理解する上で、非常に重要な鍵となります。
補足:示量変数と示強変数
最後に、熱力学で使われる物理量には、物質の量に依存する「示量変数」と、依存しない「示強変数」があることを確認しておきましょう。
- 示量変数(Extensive variable):物質の量を2倍にすると、その量も2倍になるもの。
例:エネルギー($E$)、体積($V$)、エントロピー($S$) - 示強変数(Intensive variable):物質の量に関わらず、その値が変わらないもの。
例:温度($T$)、圧力($P$)、化学ポテンシャル($\mu$)
これらの区別は、今後、熱力学的な関係式を扱う上で重要になってきます。
統計力学ノート シリーズ一覧
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。たぶん定番です。

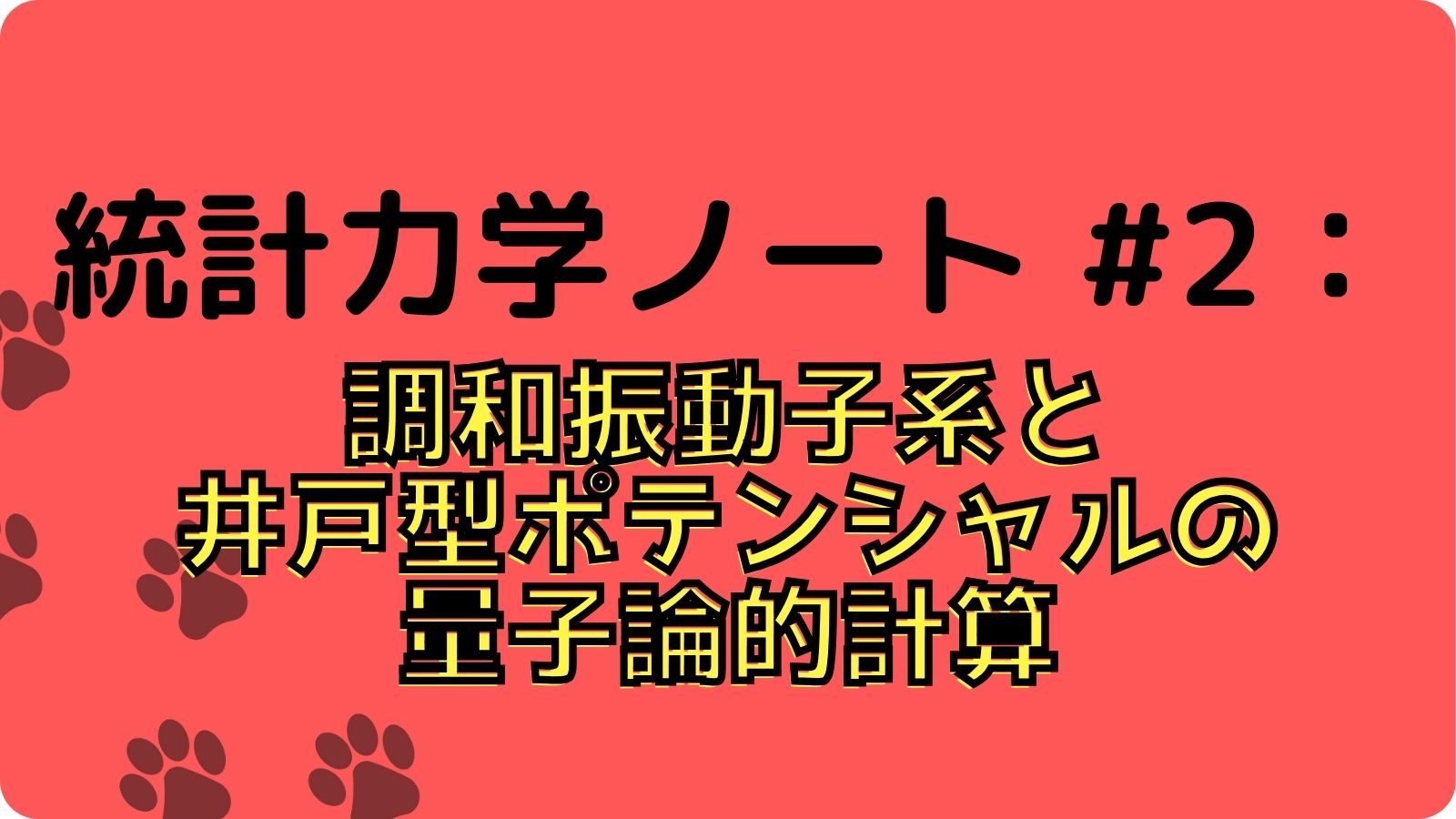


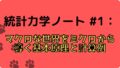
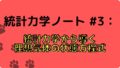
コメント