統計力学序論 #1:マクロな世界をミクロから導く基本原理と計算例
こんにちは。今回から、新しい分野「統計力学」について、個人的に学んだことをまとめていこうと思います。統計力学は、物理学の中では少し地味な分野(?)だと思われがちらしいの
ですが、物質の性質を深く理解する上で、すべての物理学を裏から支えている非常に重要な学問です。
統計力学の最大の目標は、ニュートン力学や量子力学といったミクロな理論から、アボガドロ数($6.02 \times 10^{23}$個)の粒子を含むようなマクロな物質の性質を導き出すことです。このブログでは、特にマクロな時間変化や流れがない状態、すなわち平衡系を扱います。
同じエネルギーでも状態はさまざま
統計力学を学ぶ上で、とても興味深い考え方があります。それは、同じエネルギーを持つマクロな系でも、その状態には「非典型的な状態」と「典型的な状態」があるということです。
例えば、部屋の空気のエネルギーが一定だとします。このとき、考えられる状態の数には、空気が部屋の片隅に偏っているような「非典型的な状態」も含まれます。しかし、私たちが日常的に目にするのは、空気が均一に分布している「典型的な状態」です。
統計力学では、ここで大胆な仮説を立てます。
それは、「同じエネルギーを持つ状態のほとんどすべてが典型的な状態である」というものです。
この仮説は、理論的にも実験的にもその正しさが裏付けられているそうです。これにより、我々が観測するマクロな物理量は、ほぼすべてが「典型的な状態」の振る舞いによって決まる、と考えることができます。
統計力学の二つの主要な原理
統計力学がミクロからマクロへ橋渡しをする上で、「等確率の原理」と「ボルツマンの原理」という二つの主要な原理がとても重要な役割を担っています。
等確率の原理(ミクロカノニカル分布)
この原理は、「エネルギーがほぼ等しいマクロな系において、考えられるすべての状態は、ほとんど区別がつかないので、すべて同じ確率で現れる」という仮定です。
この考え方によると、ある瞬間の状態を調べる代わりに、同じエネルギーを持つすべての状態の平均値を計算しても、マクロな物理量(圧力や温度など)は同じ結果になるはずだと考えることができます。この原理を数式で表現したものをミクロカノニカル分布と呼びます。
ボルツマンの原理
この原理は、ミクロな世界の物理量とマクロな世界の物理量を結びつける、まさに統計力学の核心だといえるでしょう。
公式は非常にシンプルで、「熱力学で定義されるエントロピー$S$は、ボルツマン定数$k_B$と、ミクロな状態数$W$の自然対数を掛けたものに等しい」と表されます。
$$S = k_B \ln W$$
この原理を用いることで、まずミクロな理論で状態数$W$を計算し、そこからマクロな量であるエントロピー$S$を導き出すことができます。さらに、熱力学の知識と組み合わせることで、「温度$T$」を次のように定義することもできるそうです。
$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$
この二つの原理が、なぜ個々の粒子のランダムな振る舞いから、系全体として決まった振る舞い(温度や圧力など)が生じるのか、という統計力学の根本的な考え方をなしているようです。
二準位系で学ぶ統計力学の計算手順
これらの原理を実際にどう使うのか、とても簡単なモデルである「二準位系」を例に、その基本的な計算手順を追ってみました。
まず、エネルギー準位が二つだけ($ \epsilon_1, \epsilon_2 $)存在する系を考えます。この系には$n$個の粒子があり、それぞれがこの二つの準位のどちらかに存在するとします。下側の準位にある粒子の数を$n_1$、上側の粒子の数を$n_2$とすると、系の全エネルギー$E$は次のようになります。
$$E = n_1\epsilon_1 + n_2\epsilon_2$$
また、$n_1+n_2 = n$なので、$n_1$と$n_2$は独立ではありません。
計算手順
- 状態数$W$の計算全エネルギー$E$が固定されたとき、どのような状態があり得るかを数えます。これは、全粒子数$n$から、上側の準位にある粒子$n_2$個を選ぶ組み合わせの問題になります。したがって、状態数$W$は次の式で計算できます。
$$W = {}_{n}C_{n_2} = \frac{n!}{n_2!(n-n_2)!}$$
- エントロピー$S$の計算次に、ボルツマンの原理$S = k_B \ln W$を使ってエントロピーを求めます。このとき、数式を簡略化するために、大きな数$n$の階乗を近似するスターリングの近似式($\ln n! \approx n\ln n – n$)を使います。
- 温度$T$とエネルギー$E$の関係導出$S$を$E$で微分することで、温度$T$との関係式$1/T = \partial S / \partial E$を導き出します。
- 比熱$C$の計算最後に、エネルギー$E$を温度$T$で微分して比熱$C$を求めます。
$$C = \frac{\partial E}{\partial T}$$
この計算の結果、比熱は温度に対して、あるピークを持つグラフになることが示されていました。この一連の手順は、統計力学の基本的な問題解決の流れであり、ミクロなモデルからマクロな物理量を導出する、という統計力学の目標を達成していることが分かります。
これまでの古典力学とはまた違った、確率や統計といった考え方が多く出てきて、とても新鮮に感じました。次回も引き続き、統計力学を進めていけたらいいなと思います。
統計力学ノート シリーズ一覧
参考文献
記事を書くときに、部分的に参照したので載せておきます。たぶん定番です。

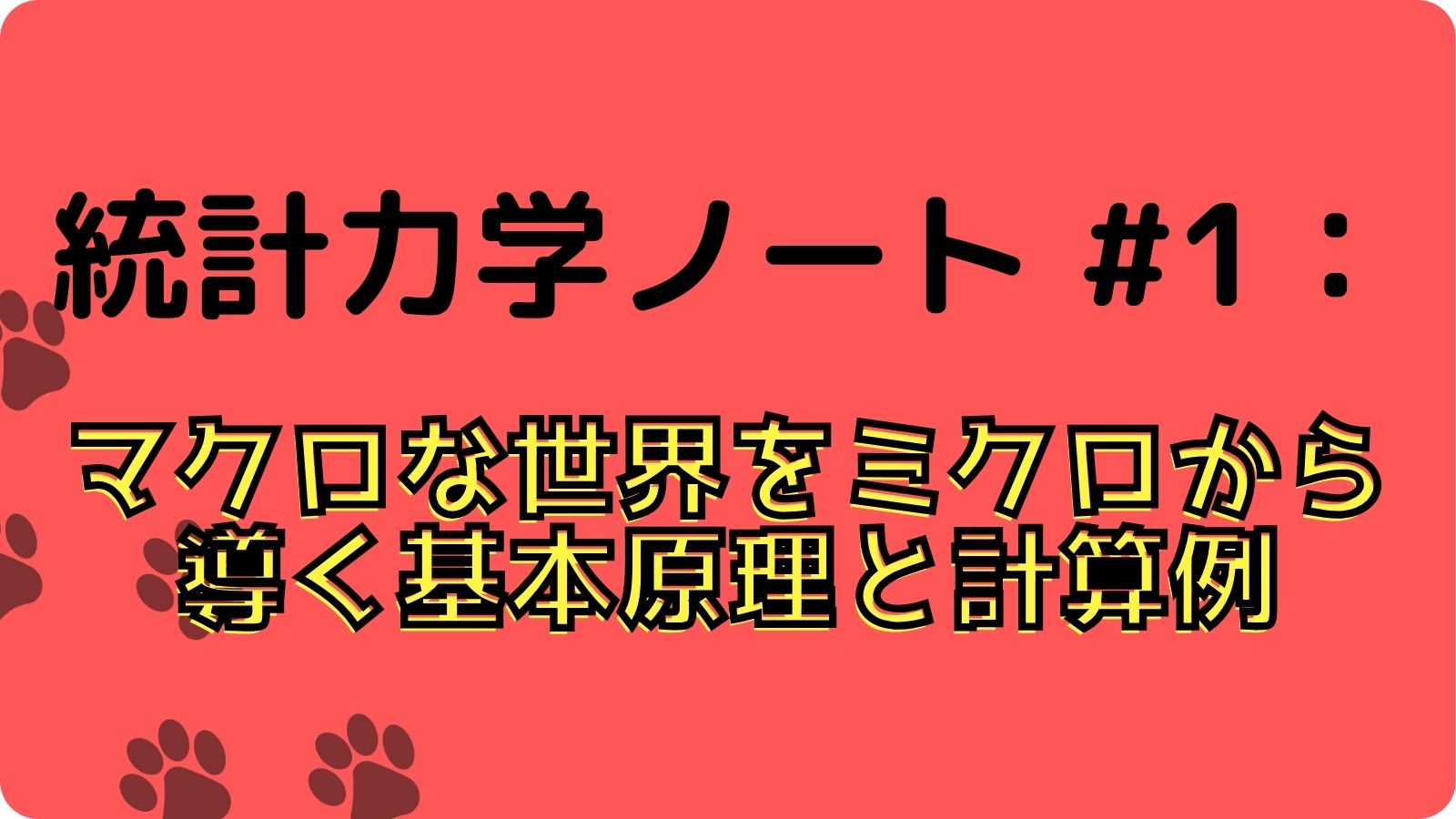



コメント